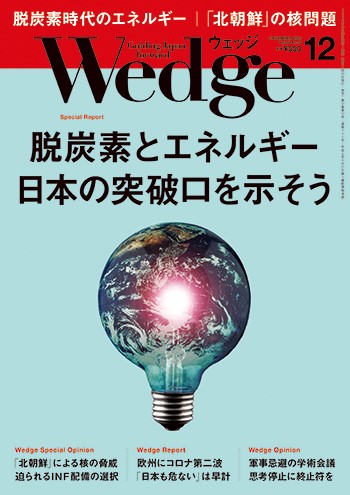11月10日に停戦合意したアルメニアとアゼルバイジャン間のナゴルノ・カラバフ紛争では、フランスがアルメニア側に立って政治介入し、アゼルバイジャン側のトルコと対立していた。背後にあるのが、フランスが抱える有力なアルメニア系市民の存在だ。
歴史は第一次世界大戦に遡り、フランスは大戦中に行われたトルコによるアルメニア人大量虐殺(ジェノサイド)を非難しており、2001年、法的にジェノサイドを認定した。06年には、シラク大統領(当時)がアルメニアの首都エレバンで「すべての国は、悲劇と過ちを認めることによって成長する」とトルコを批判する演説を行っている。
このジェノサイドにより、トルコから避難する約3万人のアルメニア人を受け入れたのが、フランスだった。現在、フランスには約60万人のアルメニア人やその子孫が在住し、その数は西ヨーロッパ最大規模に達している。
シャンソン界の巨匠で、18年に他界したシャルル・アズナブールや、1998年のサッカー・ワールドカップを制したユーリ・ジョルカエフ氏ら、アルメニア系フランス人の著名人も多い。
昨年2月、「4月24日をジェノサイド記念日に制定する」と公言しているマクロン大統領は10月1日、トルコが300人の傭兵や聖戦士をアゼルバイジャンに派遣したとし、「トルコは一線を越えた。受け入れ難い」と非難した。
これに対し、トルコのエルドアン大統領は「米露仏3カ国は、アルメニアに武器支援している」と抗議。その後、フランス各地で相次ぐイスラム教徒によるテロ事件でさらに溝が深まり、フランス製品の不買を訴えるなど、事態はエスカレートした。
パリ市内では10月25日、アルメニア人コミュニティが4度目のデモを主催。アラ・トラニアン代表は「アルツァフ(ナゴルノ・カラバフ)の人々は、生き残るため、そして民主主義のために闘っている」と主張している。
アルメニア人を庇い、トルコと敵対するほど、フランスは国内にいる欧州最大のイスラム教徒を敵に回すことになる。マクロン大統領は就任以来、最大の修羅場に立たされている。
■脱炭素とエネルギー 日本の突破口を示そう
PART 1 パリ協定を理解し脱炭素社会へのイノベーションを起こそう
DATA データから読み解く資源小国・日本のエネルギー事情
PART 2 電力自由化という美名の陰で高まる“安定供給リスク”
PART 3 温暖化やコロナで広がる懐疑論 深まる溝を埋めるには
PART 4 数値目標至上主義をやめ独・英の試行錯誤を謙虚に学べ
COLUMN 進まぬ日本の地熱発電 〝根詰まり〟解消への道筋は
INTERVIEW 小説『マグマ』の著者が語る 「地熱」に食らいつく危機感をもて
INTERVIEW 地熱発電分野のブレークスルー 日本でEGS技術の確立を
PART 5 電力だけでは実現しない 脱炭素社会に必要な三つの視点
PART 6 「脱炭素」へのたしかな道 再エネと原子力は〝共存共栄〟できる
![]()
![]()

▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。