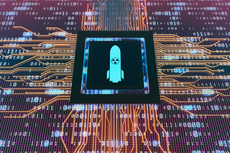筆者は20年以上、北欧諸国で毎年、水産資源管理を最前線で見て来た経験を踏まえ、2012年5月~15年3月にWEDGE Infinityで「日本の漁業は崖っぷち」を連載。特にノルウェーを中心とする北欧と日本の水産資源管理の違いをご紹介しました。
この度、編集部から連載再開の依頼を受けて連載タイトルも含めて装いも内容も新たに7年ぶりに執筆を再開します。この間、20年に改正漁業法が施行されるという前進がありました。しかしながら、資源評価やTAC(漁獲可能量)の設定、漁船や漁業者に漁獲枠を配分する個別割当制度(IQ他)を始め、科学的根拠に基づく国際的に見て遜色がない水産資源管理は、まさにこれからという段階です。
日本とノルウェーではTACの中身とその運用が大きく異なります。また、北欧の漁業や水産関係者にとっては、日本の現状には関心が高く、「日本と同じ轍を踏んではならない」ケースに写っています。
この期間に、世界では17の目標からなる持続可能な開発目標(SDGs)が15年に国連で採択されました。その中には14「海の豊かさを守ろう」が設定され、世界はその目標に向かっています。その中で水産資源に最も重要な14.4「MSY(最大持続生産=魚を減らすことなく獲り続けられる最大値)に基づく資源管理」が、北欧・北米・オセアニアといった漁業での先進国においては、多くの魚種で達成されて行きました。ところがわが国では、多くの魚種で資源の減少が止まっていない状態です。
漁獲量が大きく減った例は、サケ、サンマ、スルメイカ、イカナゴ、ハタハタをはじめ枚挙にいとまがありません。また、数十年単位でみると漁獲量が激減しているニシンのような多獲性魚種のように、かつて年間で50万トン前後獲れていた魚種が、1~2万トン獲れた程度で「資源量が高位で増加」といった資源評価がなされている魚種もあります。
かつて多くの水揚げで漁業や水産加工で潤っていた地方の衰退に歯止めがかかりません。魚が消えて行く原因は、マイワシ漁の大幅な減少と遠洋漁業の減少、もしくは海水温の上昇や、外国の漁船が日本の周りで漁獲しているからなどと思われていることでしょう。特に正しく理解されていないことが少なくない最後の2点については、別の投稿で詳述する予定です。
国際的な視点で魚が消えて行く原因を俯瞰すると、その漁獲量の傾向も含め「全く」違った状況が見えてきます。本連載では、客観的な事実をもとに「日本の漁業 こうすれば復活できる」という方法や道筋を、ファクトベースで解説していきます。そして、マスコミを含めて多くの読者に「魚が消えて行く本当の理由」に気付いていただき、SDGs14「海の豊かさを守ろう」を達成し、再び日本の海の水産資源を回復させる舵が取られることに期待しています。