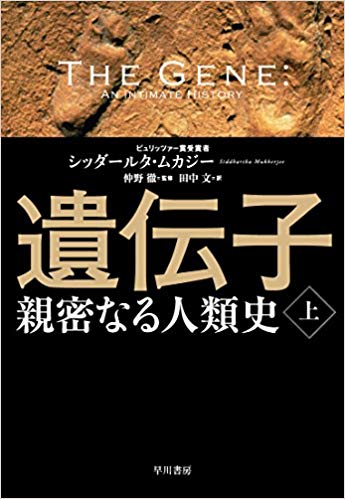19世紀後半にメンデルが発見した遺伝の法則、ダーウィンの進化論、そして、ナチスドイツが利用した優生学による「民族浄化」、第二次世界大戦後のワトソン、クリックによるDNA二重らせん構造の発見。
やがて、遺伝子組み換えやクローニングなど、急激な研究の進展に危機感を覚えた科学者たちによるアシロマ会議へと、歴史は動く。モラトリアム解禁後は、世界を巻き込んだヒトゲノム解読競争、ポストゲノムのエピジェネティクス研究、さらには山中伸弥教授らによるiPS細胞樹立、そしてゲノム編集の時代へ。
遺伝子の発見から、解読、編集にいたる「遺伝子全史」が、あますところなく網羅されているといっていい。
遺伝的多様性の価値を訴える
とはいえ、本書が教科書的な「全史」にとどまらず、心に訴えるノンフィクションとなったのは、第一に、インド出身の著者が、自らの家系に潜む精神疾患の実話を底流に描くことで、全人類の物語を切実で私的な物語に変貌させたことによる。
第二に、優生学を悪用した政策の犠牲になった人たちの実話を丁寧にとりあげ、彼ら・彼女らの顔や声を借りて、その是非を読者に問うていることによる。
たとえば、1920年代に「てんかん患者と知的障害者のためのバージニア州立コロニー」に強制的に送られたエマ・バックとキャリー・バック母娘の物語。コロニーでは、「『痴愚や魯鈍』に分類された女性たちが日常的に断種手術を受けた」という。
口絵に、セピア色の母娘の写真が掲載されている。一見すると、微笑ましい母娘のツーショット。しかし、キャプションには、「母と娘の何気ない瞬間をとらえるという口実で入手されたこの写真は、キャリーとエマがいかに似ているかを示す証拠として、つまり『遺伝的な魯鈍』を証明するために提示された」とある。
このように優生政策や人種差別、性差別は、顔かたちを変えて執拗に、くりかえし歴史上に現れる。著者は本書の全編を通じて、それに異議を唱え、遺伝的多様性の価値を訴える。
<アメリカやヨーロッパの優生学者は、人間の「良さ」を促進するために、「良さ」を人為的に選択すべきだと主張していたが、自然界では唯一の「良さ」というものは存在しない。生物集団には多種多様な遺伝型が存在し、さまざまな遺伝子のタイプが共存し、ときに重複している。人類優生学者の考えとはちがって、自然は遺伝的多様性をなくすことを望んではいない。>