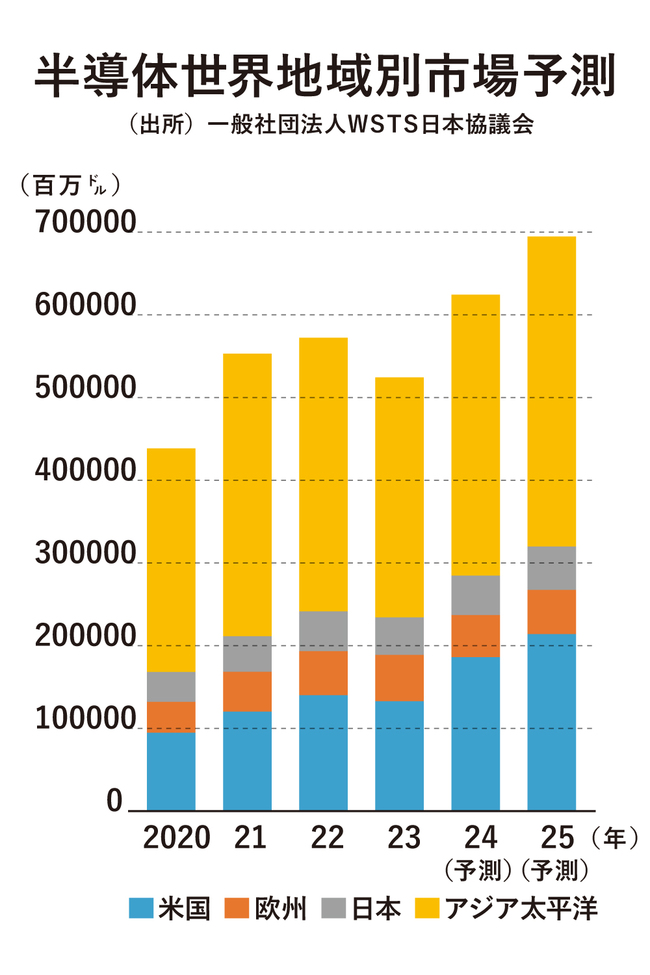今、半導体市場を牽引するのはAIである。その処理に使われているのが、GPU(画像処AI理半導体)であり、エヌビディアのシェアは8割を超す。今年1月に発表されたエヌビディアの昨年8~10月期決算での純利益は、193億900万ドル(約3兆円)で、インテルとは対照的だ。エヌビディアはGPUというハードに加えて、「CUDA(クーダ)」というソフトウェアを提供することで、GPUを使ったAIの開発支援まで行い、ハード・ソフトの両面から囲い込みを進めている。この牙城を崩すことは容易ではない。
製造に関しても課題がある。昨年11月、チップス法に基づき米商務省からインテルに78億6500万ドルの助成が確定した。「チップス法」とは、経済安全保障の観点から、前バイデン政権時代の22年、米国内での半導体製造を増やす目的で制定された法律だ。インテルはこの助成金を、オハイオ州ニューオルバニー、アリゾナ州チャンドラーなどでの先端半導体の製造設備建設に振り向ける。
だが、製造に携わる人材を米国内で確保することができるのかという課題がある。これはインテルだけの問題ではなく、チップス法で助成を受けるTSMCやサムスンも同じだ。米国の製造業において、世界市場で競争しているのは自動車産業くらいだ。
半導体の製造は、三交代制でフル稼働する過酷な現場である。TSMCでは、博士号を持つ設計部門の新入社員でも、最初は製造現場を経験させる「現場主義」を貫いている。人種で優劣をつける時代ではないが、今でもこうした製造現場はアジア系が得意とするところだ。
ではインテルの成長戦略には、どのようなものがあるのか。一つ挙げるとすると、「ASIC(Application Specific Integrated Circuit)半導体」がある。これは、自動車、通信機器、産業機器、AIサーバー市場など、特定用途向けにつくられる半導体だ。
インテルはパソコン向けの汎用半導体で未だに、世界トップシェアを走る。こうした汎用だけでなく、個別の顧客向けにカスタマイズするASIC半導体を生産すれば、設備の稼働率を上げることもできるし、これまでインテルが培ってきたIP(知的財産)を使用できることは、ユーザー側にもメリットになるはずだ。
JASM、ラピダス
日本勢はどう戦う?
TSMC熊本工場の運営子会社JASM(熊本県菊陽町)が昨年12月末に量産を開始した。当初は、28〜22 nmの汎用半導体を製造する。第一工場には日本政府も最大で4760億円の補助を行う。主な顧客は、スマートフォンのカメラに使用されるCMOSイメージセンサーを製造するソニーなどだ。足元ではその顧客であるアップルのiPhoneの成長が鈍化していることが懸念材料だが、世界中に顧客を持つTSMCだけに、工場の稼働率を維持し、安定供給することには長けているだろう。
今後は6nmを製造する第二工場の建設も予定されている。自動車に使用されるのも、このサイズが主流になってくることを考えると、適切な投資だといえる。
もう一つは、ラピダスだ。こちらも、日本政府が累計で1兆円規模となる補助金を出す。昨年12月には最先端EUV装置をASMLから納入した。この装置は極端紫外線を使用するため、高度な技術が必要とされ、扱いが難しい。千歳市にASMLがオフィスを開設したことでサポートを受けるほか、現在、同社からは100人に上る従業員をニューヨーク州オールバニにあるIBMの研修施設に派遣している。