緊急事態宣言が解除された。メディアが伝える街の声は「解除されるのが待ち遠しい」「もう少し我慢する必要があるのでは」というもので、ストレスフルで厳しい自粛生活に耐えてこそ命が守れるのだという前提が揺らぐことはなかった。
現代社会は、膨大な人間の膨大な活動が複雑に絡み合い、全体が高速でうごめくことで維持されている。ところが今回、強制スリープ状態が訪れた。わたしたちは経済活動が止まった世の中を目の当たりにし、お金を得ることが難しくなっただけでなく、外でお金を使うことも難しくなった。これと「新しい生活様式」が相まって、これまでとは段違いのシンプルな生活を余儀なくされ、それを自分なりに味わう人が増えてきた。
これを筆者は、コロナ自粛による功罪の「功」だと捉えている。今回は、「自家製の楽しみを生み出す動き」と「集まる価値の見直し」の2つの例を紹介したい。
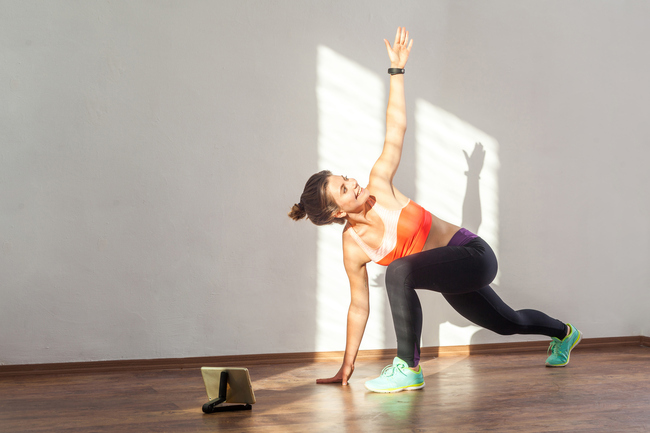
自家製の楽しみを生み出す
3密を避けることを目的に社会が変化したことで、不可避だと思われていた満員電車という移動状態は避けるべきものだと定義された。なくなってみれば「あんな日常に戻りたくない」となる。しかし一方で、高密度空間と楽しみが混然一体となっている店やイベントなども休止となってしまった。こうした「誰かの提供してくれる娯楽」が元通りの形で提供されるまでにはまだまだ時間がかかる。
暇つぶしのネタを渡り歩いてもいずれ飽き、虚しさばかりが募る。そんな時、外の状況に左右されない楽しみを携えていることは、大きな強みとなる。
振り返れば、田舎に暮らす人ほどコロナ自粛による精神的ダメージは少なかったように見受けられる。そもそも密度の低い場所はクラスターの危険性が低く、のんびりしているということもあるが、それだけではないと感じる。筆者が二拠点生活を営む千葉県南房総市では、コロナ以前とそれほど暮らしぶりは変わらない。
二拠点生活の友人らもそれぞれ、田舎での自分の暮らしを楽しんでいた。家から家の往復以外の立ち寄りができない不自由はあれど、いつもより多めに手に入れた自由時間にしたいことがどんどん詰め込まれていく。「季節の野菜くらいは自分のところで賄えるようになるぞ」と畑の拡大を目指す農作業の人。「去年の台風で壊れちゃったところを直すついでに」と屋根付きバーベキュー場づくりに励むDIYな人。とりあえず2週間は誰とも会わず、その後はロードバイクで半島をまわって体力を維持しながら長期山村リモートワークに臨む人。ニョキニョキッと生えてくるタケノコを大汗かいて掘り出しては灰汁を抜き、大量にメンマをつくってにんまり笑う人。自粛生活への不安や焦燥感などが顔を出す余地はなさそうだ。
以前なら「そんなことにかまける暇な人」に見えていたかもしれないが、withコロナを経た今となっては見る目が変わる。お金で買えない価値が本領発揮する局面だったからだ。だいたいの楽しみがお金で買えていた時代には、あるのは知っていてもなかなか本気で見えてこなかった価値である。

















