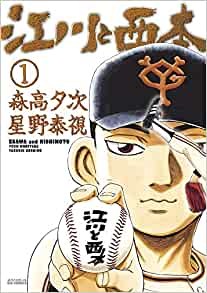そこに理屈はない。利害やメリットデメリットといった計算もない。ネタバレにならないように詳細は伏せるが、最終的に生徒たちが巣立っていった後、弟子たちの心に残ったのはこの「描け」というただ一つのメッセージだった。このような環境で育まれたからこそ、「絵画」と「漫画」という、本来は技術や環境とも対局にある世界で、東村氏は折れることなくやり続け、圧倒的な成果を出し続けられたのだ。
これらの話は、本連載で今までに語った合理性やサイエンスとはかけ離れた、いわゆる「体育会礼賛」な話に見えるが、私はこのスタンスに一定、賛成している。要するに、両方を知った上での使い分けなのだ。また別の推薦図書で、『日本辺境論』(新潮新書、内田樹)というものがあり、そこでは人の学びの本質について述べられている。赤ちゃんは生まれてから、興味津々で色々なことに触れて学んでいくが、ここで彼・彼女らは別に、学びの必要性や意味、意義などは考えていない。あるのは、生まれ落ちて目の前に広がる、様々な世界への純粋な好奇心だ。つまりは、無垢な状態でピュアなまま学び続けるのが学びの本質であり、最も成長に繋がるのだ、ということが述べられている。
近年、板前や寿司職人といった現場での、非合理的な師弟関係がバッシングされることがあるが、一定までは、この「GRIT」を鍛えるという意味でも、このような環境の意義はある。要するにバランスなのだ。
「体育会系」の現場からも学ぶことが
なお他の漫画作品だと、読売巨人軍を描いた『江川と西本』(森高 夕次 〈著〉 星野 泰視 〈イラスト〉小学館)にもそれが色濃く表れている。具体的には7巻だ。ミスター巨人こと長嶋茂雄監督が、低迷する巨人軍を鍛え上げるために、鬼軍曹のようなトレーニングを選手に課す。過酷な合宿を行い、日没後にボールが見えない中でも、「心を鍛える練習」といって徹底的に、非合理的な千本ノックを強いる。これに限らず、数百回の投げ込みや腹筋、走り込みなど、「こんな練習やる意味あるのか、辛いだけじゃないか!」と思われるようなことを、無理矢理やり切らせる。あまりに辛すぎる合宿だったと思うが、これをやり遂げた選手たちの達成感はひとしおで、甘えが消え、精神的に成熟し、これにより、若手の急速な成長と強化に繋がるのだ。残念ながら、チーム成績として成果が上がるのは、長嶋監督が辞任した後なのだが、辞任直後の81年〜83年に1、2、1位という連続した好成績を収めたのは、間違いなくこの時の長嶋監督による、若手の底上げとなる「鬼トレーニング」の成果である。
近年では悪しきとされる、非合理的な体育会の環境。この際、この価値も「合理的に」見直してみよう。辛い環境下でも逃げずにやり切ることで、「GRIT〜やり抜く力」を育てるというアプローチは、自身の生き様や部下の育成、子供に与える環境などに、この上ない参考になるはずだ。
最後に、東村アキコ氏の過去のインタビュー内容を抜粋しておく。
「どうやって「美大に合格したか」「漫画家になれたか」とよく若い子に聞かれるが、絵を描くということは、ただ手を動かし「描くこと」、「どれだけ手を動かしたか」が全てです」(『パピルス』「東村アキコ 神様は、降りてこない」2013年8月号 幻冬舎)