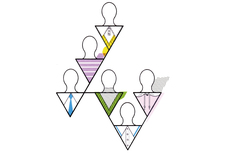英国のグラスゴーで行われた今年の第26回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP26)は、久しぶりに注目されたCOPとなった。過去最も注目されたCOPは、2009年にデンマークのコペンハーゲンで行われたCOP15である。このCOPは、「ポスト京都議定書」と言われた京都議定書後の枠組みを決める重要な回だったが、議論が紛糾して合意文書の「採択」ができず、最終的に「留意する(take note)」という苦肉の策で終わった。

このことは、COPの国際交渉の歴史における〝最大の失敗〟と言われている。その後、世間のCOP交渉に対する関心は次第に低くなっていった。15年のCOP21で、新しい枠組みとなるパリ協定が採択され再び注目されたものの、それ以降のCOPが大きくメディアを賑わせることはなかった。
今回のCOP26がこれほど注目されたのは、19年から20年にかけて起きた「国際的な脱炭素トレンド」以降、はじめて開催されたCOPだからである。特に、筆者に来る問い合わせや取材を受けて感じることは、さまざまな業界の関心が非常に高いということと、その一方でそうした事業者の実務的な関心とメディアの関心のポイントのズレが非常に大きいということである。
恥ずべきことではない日本の「化石賞」
従来、日本の温暖化政策の文脈では、「日本が世界にアピールできる高い削減目標を自ら設定して称賛されることで、それをテコに強く他国にも働きかけ、世界の気候変動政策においてリーダーシップを発揮する」、つまり外交上の「点数」を稼ぐことが求められていると考えられていた。
従って、毎回受賞される「化石賞」は、他国から称賛されていないことを示すわかりやすい話題であり、日本のメディアはこれを政府の失点として必ず取り上げる。筆者は実際、今年もメディアから「化石賞受賞についてどう思うか」、「日本の存在感はあったか」、という問い合わせを受けることが最も多かった。
しかし、このような視点でCOPにおける日本の立場を評価することは、次に述べる2つの点で的外れである。