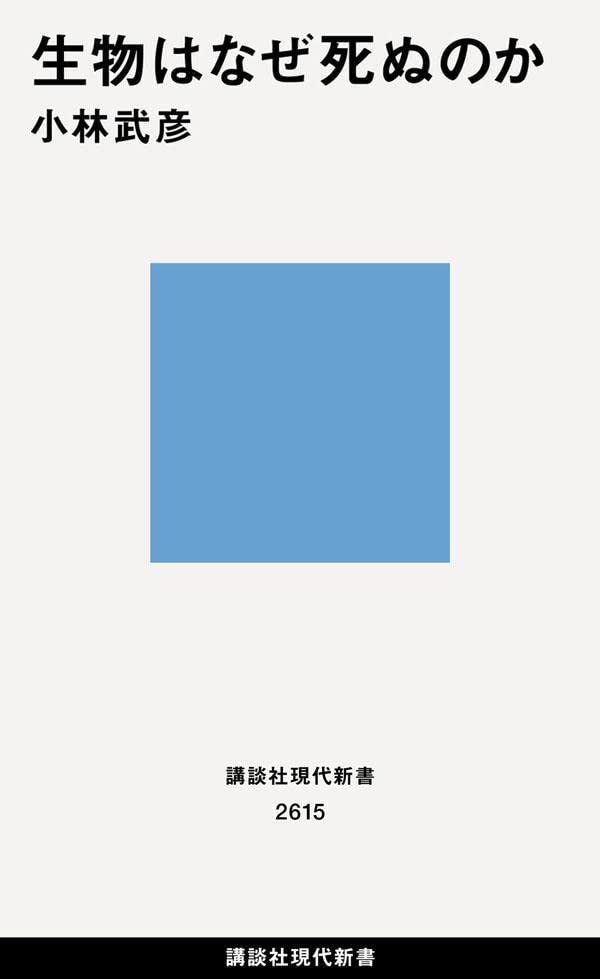大ベストセラーとなった『生物はなぜ死ぬのか』(講談社現代新書)の著者で生物学者の小林武彦東京大学教授。「死」は生物が進化し、多様性を持つために必要な次世代への「Turn Over(生まれ変わり)」であると説く。
寿命で死ぬことはネガティブなことではなく、生物は死ぬからこそ、進化したというポジティブな側面がある。かつて遺伝情報を担っていたRNA(リボ核酸)は、反応性に富み、自己複製したり、変化しやすい一方で、壊れやすいという性質を持っているが、壊れることで新しい材料となる。生物には、その根源部分で「壊れる=死ぬ」というメカニズムが備わっている。
小林教授に、なぜ人は死に抗うのか、そして、死なない知性であるAI時代の到来について聞いた。

「死」が進化にかかわっていることは「世代交代」という言葉があるように、感覚的には多くの人が理解できることだと思う。われわれ生物学者にとっては当たり前のことではあったが、「死」をポジティブに発信するということはあまりなかった。といっても、だから安易に死んでもよいということではない。
多くの生物は、生殖機能の維持と寿命が一致している。ところが、人間は生殖機能が衰えた後でも生き続ける。「おばあちゃん仮説」と呼ばれるように、教育したり、子育てを手伝ったりするために長生きをするという見方もある。人間の場合、寿命の長さは社会環境にも大きな影響を受けている。
大まかにいえば、人間社会は若者が自由に創造性豊かに活動し、その土台をシニア世代が支えるという構造で成り立っている。だからこそ、若者が寿命を待たずして死ぬことは、人間社会にとってマイナスとなる。
進化にとって「死」が必要であることは遺伝子レベルで組み込まれているにもかかわらず、その意義が実感しづらいのは、「地動説」などと違って、それを確認することができないからだ。例えば、人間とチンパンジーの遺伝子の違いは1・5%しかない。しかし、遺伝子が1%変化するのに600万年、30万世代という、途方もない時間と、「Turn Over」が必要になる。
感情が進化して「死」に慣れることはできなかったのか?
生物の仕組みとして「死」が組み込まれているのであれば、人間も進化のプロセスの中で、感情として「死」を恐れないようにできなかったのか、という質問がある。
それに答えるならば、「死」への恐れがないと生きることができないからだ。死を恐れるのは人間だけではない。植物でも、昆虫でも「逃避本能」があることは確認されている。例えば、植物は青虫に捕食されるときに、青虫の消化を悪くする物質を出す。マグロのように99%以上の稚魚は捕食されたとしても、やはり逃避本能はある。逆に言えば、「死」があるからこそ、一生懸命生きようとするのだ。
それでも、死は怖い。特に知能の発達した人間はそうだ。だからこそ、その怖れを皆で癒やしたり、共有しようとしたりするために宗教が生まれたともいうこともできる。
一方で昨今目立っているのが「アンチエイジング」「ゲノム編集」「マインドアップロード」、果ては「不老不死」に向けた研究だ。私自身、研究者として研究すること自体は賛成である。だが、これが社会全体に広がった場合、大きな危険をはらむことになると思う。
というのも、お金持ちだろうが、なんであろうが「死だけは平等」というのが人間社会の不文律だったからだ。だからこそ、人間社会には一定の「連帯感」があった。ところが「お金持ちは長生きで、そうでない人は短命」などということが現実に起きてしまえば、そのバランスが崩れてしまう。
歴史を振り返ってみれば、お金持ち(成功者)は、その財産を死後に持っていくことができないからこそ、せめて名だけでも残そうと、さまざまなところにドネーション(寄付)を行った。つまり、富裕層の富が社会性のある使われ方をしていた。ところが「不老不死」の研究は、富裕層の富が、その個人のためだけに使われてしまう可能性がある。
サイエンス全般にも同じことがいえるように思える。医薬、電気、自動車、食糧など、今までのサイエンスは、社会幸福の増大に貢献してきた。しかし、「お金持ちはより健康になれる」「頭の良い人はより良くなる」といったことにサイエンスが使われる可能性がある。このような研究者は、かつては「マッドサイエンティスト」と呼ばれたものだが、節度を持った研究をしてほしいと願うばかりだ。