近現代史への関心は高く書物も多いが、首を傾げるものも少なくない。相当ひどいものが横行していると言っても過言ではない有様である。この連載「近現代史ブックレビュー」はこうした状況を打破するために始められた、近現代史の正確な理解を目指す読者のためのコラムである。
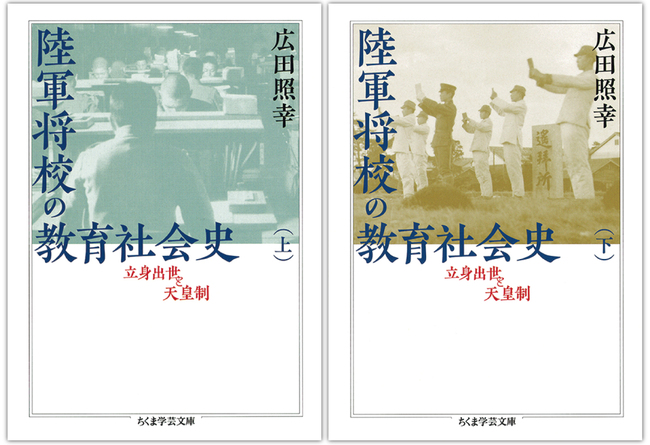
本書は歴史資料はもちろん、特に正確な統計資料をもとに初めて近代日本の陸軍将校の形成システムを明らかにした画期的な書物である。
本書の取り扱う領域は極めて広いので、ここではその中から、これまで統計的研究がなく、実態が明らかでなかった陸軍士官学校(以下、陸士)の志願者の変遷という興味あるそして重要な論点を見ていくことにしよう。
陸士は1874年に設立され、一時期志願者が減少したが、92年ごろから増加に転じ、94年の日清戦争勃発を契機に激増。日清戦争の勝利が青少年の軍事崇拝熱を生み出したのである。ところが、日清戦争で急増した志願者数は、日露戦争直前までには少しずつ減っていった。
しかし、日露戦争の勝利により「軍人株」は大いに上がり、日露戦争後志願者数は再び激増、1910年代半ばまで過去最高を更新し続けていった。志願者数は1916年にピークを迎える。ところが、第一次世界大戦末期から軍人人気は急速に低落、第一次大戦中の4000人程度から21年には1109人にまで落ち込む。22年、陸軍系の団体の雑誌記事には、生徒志願者数の不振について指摘がされているが、それらは概ね妥当だと著者はいう。
すなわち、①将校となっても退官が早く生活が不安である、②物質主義的傾向が非常に強くなってきて、収入の多寡を職業選択の基準にするようになってきた、③規律の厳粛な将校を希望しない、④何よりも平和主義が強くなった結果、軍隊無用論がマスコミなどに極めて多く流れていた。軍縮とデモクラシーの台頭は軍人という職業を不必要で古めかしいものと思わせたというわけである。

















