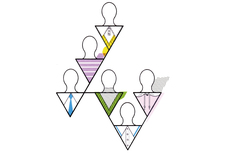2013年に習近平氏が古代のシルクロードに範をとる「一帯一路」を提唱してから10年、『人民日報』は敦煌仏教美術の中から飛び出してきた飛天像と白鹿が世界中の一帯一路インフラの現場をめぐるというCG動画「絲路画巻(シルクロード絵巻)」で、その豊富な成果を誇示した。
そして去る10月18・19日に開催された第3回一帯一路サミットと、それに合わせた習近平氏と各国首脳との会談では、「百年に一度あるかないかの国際秩序の激変が続く中、国の大小や制度の違いを問わずWin-Winの境地と人類運命共同体を目指す」中国の指導力に対する賞賛があふれた。
いっぽう日本における一帯一路をめぐる報道は、主に中国が途上国を借款漬けにして、返済不能に陥った国に対し長期にわたるインフラの排他的な租借を要求するといった展開を批判するものが目立つように思われる。筆者は、確かにこの種の問題も重大だと考えるが、今回の一帯一路サミットを取り巻くより重要な変化として、これまで一帯一路に参加してきた諸外国が依拠してきた価値観や秩序・国益と、実際の一帯一路の展開との間に隙間が生じている問題に注目したい。
一帯一路への参加国が減っている事実
まず一帯一路は、サミットにおける首脳陣や国際組織の変遷をみれば、変調をきたしていることは否めない。具体的な数字を挙げると以下の通りである。
第一回(2017年5月)……29カ国の首脳参加。140余カ国、80余の国際組織、計1600人以上。
第二回(2019年4月)……38カ国の首脳参加。150余カ国、90余の国際組織、計5000人以上。
第三回(2023年10月)……24カ国の首脳参加。151カ国、41の国際組織。登録者数は1万人以上。
このような変化の背景にあるものは何か。
一つは、新疆・香港問題をはじめ中国の人権・自由を取り巻く問題が噴出して以来、西側諸国と中国との間でデカップリング(経済関係の切り離し)、あるいはデリスキング(経済的リスクの低減)が進んだ結果であろう。
中国は、各国ごとに異なる体制を互いに尊重しつつ社会の安定を実現させ、経済を発展させ、結びつきを強めれば、自ずとWin-Winの運命共同体の境地を外国と共有し、さらに人類運命共同体へと昇華させうると説く。しかし、中国が「社会の安定」のために用いる手段や制度が外国の規範意識から見て非道徳的であり、その中から生み出された経済的利益が商業道徳とそぐわないとすれば、そのような中国との経済的関係の是非そのものが問題となる。
また、中国の内政のあり方やデカップリング・デリスキングや疫病の影響もあって、中国経済の先行きが不透明になったことの影響も大きい。中国で失業者の増加や金融機関・不動産会社の破綻などの問題が山積する中、一帯一路を「無原則的なばら撒き」と見なす冷淡な雰囲気が急速に広まりつつある。