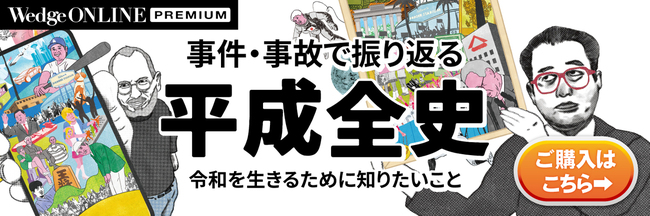代償は我々と次世代の子ども達に
ALPS処理水問題では、海洋放出直後、中国とロシアが日本産海産物の輸入を禁止しておきながら、日本近海に漁船を送り続けた。科学的事実など百も承知の上で「汚染」を喧伝したということだ。
24年には魚介類が汚染されていないことを認めているが、輸入再開時期の具体的目途は立っていない。懸念されていた風評問題も、中露による「汚染」情報の拡散や輸入禁止措置など政治的問題を除けば概ね起きなかった。
海洋放出後に風評問題が拡大しなかった背景には、主に2つの要因が挙げられる。
1つ目は、経産省と外務省が、従来の行政にしばしば見られた、単にパンフレットやホームページで告知するだけに留まらず、自ら積極的に働きかける周到な説得と根回しを繰り返した。
2つ目は、特に外務省が、中国政府などの偽情報に前例がないほど真っ向から強く反論し、SNS上で広がったデマも具体的に取り上げながら何度も否定し続ける「攻め」の広報に転じたことだ。
一方で、長期にわたる「汚染」喧伝によって時間やリソースが奪われ、政府は風評被害対策として企業の食堂への水産物の提供や広報活動に約300億円、漁業の継続支援などに約500億円の基金をそれぞれ活用することを決めた(「処理水風評被害対策、計800億円の基金活用 必要なら積み増しも」)。廃炉作業と復興も遅延を余儀なくされたのも事実だ。
たとえ過去の問題になろうと、それらの代償は今後も長期にわたって残され、全ては我々一人ひとりの負担、電気代や税金などによって間接的に賄われる。「汚染」を喧伝した人々は謝罪すら無く、何一つ責任を取らず次のターゲットに移行し続ける。
社会は「喉元過ぎれば熱さ忘れる」かのように、それを許し続けてきた。現に処理水問題における風評加害の責任を問う声など、今や話題にもならない。
まして処理土は陸上に残される性質上、このままではALPS処理水問題以上に対策費が積み増され、莫大な禍根と負担を残す可能性が高い現状と考えられるのではないか。
世論と環境省は、ALPS処理水問題を経た経産省や外務省の経験を踏襲し、「風評加害」やマッチポンプ・クレイムを含むインフルエンスオペレーションに毅然と対応できるか否か。まさに今こそが、分水嶺と言えるだろう。