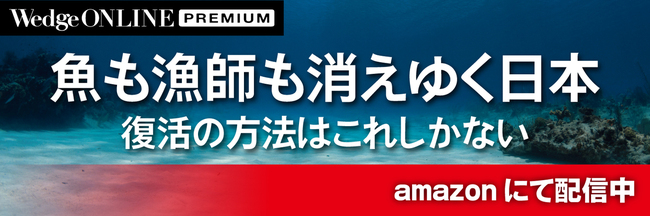さてここから、今回の漁獲枠設定の問題の本質についてお話しします。先に一応24年の公海では漁獲枠が少し機能してそれ以上の過剰漁獲がストップしたとご説明しました。
今年(25年)は、昨年(24年)の全体の漁獲枠22.5万トンに対して「10%減」の20万トンで決着しています。この中で公海は10%減の12万トンとなっており、昨年の漁獲量(14.5万トン)より約2割少なく、いくらか効果が期待できます。
ところが、この枠は公海とEEZ(実質日本のEEZ内)で2重構造になっています。昨年(24年)の計算をすると、22.5万トン(全体枠)―13.5万トン(公海枠)=9万トンが実質的な日本のEEZ内での漁獲枠です。同じ計算をすると日本のEEZ内で公海とは別に漁獲できる枠(公海でも操業可)として、日本が漁獲できる数量は約8万トン(=20万トンー12万トン)となります。
ところで24年の日本のサンマの漁獲量は約4万トン(3.9万トン)です。つまり、日本だけが昨年(24年)実績の倍の漁獲枠を持っていることになります。
誰よりも困るのはサンマを食べる日本人
国益としては頑張った交渉です。しかしながら、資源管理というもっと大きな観点からすると我が国だけで、科学者が計算した漁獲枠(7.6万トン)を超えてまっています。
すでに日本のサンマの漁獲量は全体の2割程度で推移してしまっています。かつての台湾・中国のサンマ漁進出前の8割前後ではありません。
今後、資源管理のために国別の漁獲枠の設定が不可欠となっていきます。この日本のサンマの漁獲枠が多すぎると、海外から指摘されることが予想されます。
そして何より懸念されるのは、サンマが減ってもっとも困る日本が、そのサンマを獲り過ぎてしまう漁獲枠になってしまっていることではないでしょうか。