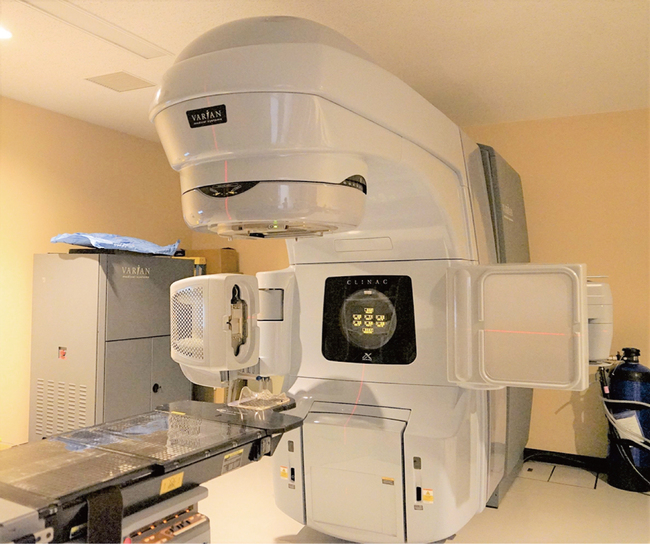回収の見込みがないまま同科を継続すれば病院全体の経営を圧迫しかねない。そうなれば、他科の患者も病院も〝共倒れ〟になる。院長として苦渋の決断だったが、そうしたリスクを避けるためにも傷口が浅いうちに撤退を決めたことは、誤解を恐れず踏み込んで言えば、妥当な判断だろう。
日本の後期高齢者は30年をピークに減少に転じると予測されているが、佐渡島では既に全年齢層で人口が減少している。佐藤氏は〝佐渡島は日本の先進地域〟と表現し、人口減少地域における医療福祉システム維持のための仕組みづくりにも力を入れる。
例えば島民の医療情報をレセプト(診療報酬明細書)などから自動収集し効率的に地域で共有する「さどひまわりネット」や、オンライン診療の導入、地域全体で病床管理を行うシステムの構築を主導した。「当事者である地域全体で考えなければならない」として、行政任せではなく関係者同士フラットに話ができる場の整備も行った。
「佐渡島では3年間で6つあった病院が2つに減少した。国は統廃合を含めた病院の機能分化を推進しインセンティブをつけて誘導するが、そのモデルは佐渡島には当てはめられない。患者の医療アクセスが犠牲になり重症化する前の患者をキャッチアップする機会を逃すからだ」
こう話す佐藤氏だが、同時に「佐渡島で人口減少に対応できる医療福祉システムがつくれれば、他地域にも貢献できる。高齢になっても一人で生活ができる社会を目指したい」と希望も捨てていない。
公的財源で民間経営
日本の医療制度の構造的難しさ
佐渡総合病院の設置者であるJA新潟厚生連は、県内の合計11病院の経営を管理する。代表理事常務である本田浩之氏は「赤字の病院があっても、黒字の病院の利益を補填する形で収支均衡を保ってきた。だが、光熱費は17年に比べて22年には約3割上昇した。コスト高を診療報酬でカバーできなくなった」と話す。
同企画管理部長の友田理氏も「医療材料は輸入品が多く、世界情勢の影響を受けやすい。公定価格は消費税を含む費用上昇を価格転嫁できない。診療報酬点数を上げる議論もあるが患者負担につながる」と、公と民が入り混じる難しさを指摘する。
新潟県は全国的にも医師不足の県とされる。本田氏は「都心よりも医師の報酬を高く設定しているが、それでも医師が集まらない」と、地方での医師確保の難しさを語った。
医局人事の問題もある。地域によっては医師の派遣元となる大学病院の「医局」に実質の権限があり、受け入れ側主導での医師の確保がしにくい。また、医療の財源は保険料と公費が大半を占める。そのため、「医療費を削減すべき」との議論があがるが、全国自治体病院協議会会長の望月泉医師は「医療費の増加は高齢化だけでなく医療の進歩によるところも大きい」と指摘する。
さらに「他国に比べて自己負担が安く抑えられるため、ドクターショッピングや〝念のため検査〟もしがちだ。だが、国民皆保険制度の維持すら難しい局面に立たされている。国はそろそろ目指す方向性をはっきりと示さなければならない」と話す。
日本の医療は誰のものか。この問いに対しては、全国民が〝当事者〟だ。私たちは、各地で起こる病院統廃合というシグナルをどう受けとめるべきなのだろうか。