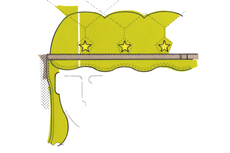11時間の外科手術を越えて
2025年の初秋、私の人生は再び試練の峠を迎えた。
大腸がんと肝臓がん、二つの病巣を同時に摘出する外科手術は、実に11時間に及んだ。執刀医をはじめ、麻酔科、看護師、リハビリスタッフ、すべての医療チームが総力を挙げた長い戦いであった。
だが、実のところ真の闘いは手術台の上では終わらなかった。むしろ、手術後の1カ月以上にわたる闘病生活こそ、痛みと不眠、そして孤独との戦いの連続であった。
医学の進歩はあっても患者の我慢が軽くなる訳ではない。「日にち薬」と言って一定の日数は独自の回復力に頼るしかないのだ。
ただひたすら我慢を余儀なくする夜は特に長い。眠剤が効かず、痛み止めのタイミングも中々合わない。昼と夜が逆転し、眠りを求めて天井の灯を数える日々が続いた。リハビリルームも閉ざされた静寂の中、唯一の運動は病棟の1階から8階までの階段をゆっくりと上り下りすることだった。ともかく、身体を動かしてると身体能力は回復が早い。
「生きるとは、痛みと共に歩くことなのか」――そう自問した日もあった。
Pain is gain リハビリは必ず役に立つ
緩和ケアという名の“生の哲学”
しかし、そんな中で私はひとつの光を見出した。それが「緩和ケア」である。
多くの人が「緩和ケア」と聞くと、終末期のケアを連想する。しかし、実際にはもっと広く、もっと“生きるための支援”である。
がんと共に生きる患者にとって、緩和ケアは治療と並行して行う「もうひとつの医療」であり、痛み・苦しみ・不安を和らげながら生活の質(QOL)を最大限に高めるための総合的アプローチである。
私の場合、痛みのコントロールが最優先課題だった。昼はカロナール、夜はロキソニン。夕方にカロナールを飲み、寝る前にロキソニンを飲む。これでぐっすり寝ることができる。医師や看護師と相談を重ね、ようやく「眠れるリズム」を取り戻した。加えて、マッサージ、軽いストレッチ、鍼灸の助言も取り入れた。
「痛みが和らぐと、心にも風が通う」――そう実感した瞬間、私は再び前を向くことができた。
痛みと心のケア ― 人間の尊厳を守る戦い
理学療法士と作業療法士の違い
がん治療の現場では、痛みや倦怠感、吐き気、呼吸の苦しみなど、多くの症状が重なって襲いかかる。
これらの症状管理には、医療チームによる薬物療法だけでなく、患者自身の生活リズムや心理状態の調整が欠かせない。私は、朝の散歩を欠かさず、食事もできるだけ自然な味を楽しむよう心がけた。慣れると生活のリズムも戻ってくる。
国立がんセンターでは2種類のリハビリがある。
理学療法士と並ぶリハビリ職の国家資格として、作業療法士(Occupational Therapist:OT)がある。理学療法士の支援対象は身体に障がいを持つ人が中心だが、作業療法士の場合は精神障がい者も支援対象に含まれる。
理学療法士は座る・立つ・歩くといった“基本的な動作”を中心にリハビリするのに対し、作業療法士は服を着替える、身体を洗う、字を書くといった日常生活での“応用的な動作”を主軸としてリハビリをおこなう。ただし、2つの領域が明確に分かれているわけではないため、理学療法士が日常生活上の作業を訓練することもあるし、作業療法士と連携しながら進めることもある。毎日30分ずつけ訓練を受けるが理学療法士は、会話をするだけだが心のリハビリにも役立っている。
つまり、心理的なケアも大切なのである。手術を終えた直後、私は自分が“もうひとりの自分”になったような感覚に包まれた。身体は変わり果て、痛みが残る。しかし、それでも心のどこかに「まだ行きたい場所がある」という想いが芽生えた。
それが、私にとっての「旅」という生きる原点だった。