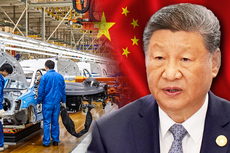本当はさ、富岡の家を買い上げて貰えばすっきりするんだよ。最初はみんな富岡に帰る気だったし、俺も長岡にいた頃は帰る気満々だったけどよ、時間がたつとだんだん帰る気がなくなるんだよ。富岡に帰るって人は、歯が抜けるように減っていったね。俺も72歳だからもう限界だよな。いまからバタバタしたってしょうがねえと思うのさ。それに年寄りばっかり帰ったって、若い人が帰らないと町はやっていけないぞ。富岡なんて町の予算の何分の一だか、東電から貰ってたんだからな。
国の偉い人にさ、家族を連れて1週間でも10日でもいいから富岡に泊まってみろって言いたいね。チェルノブイリがどうとかいうデータでなくて、どんだけ不便だか、ちゃんと現場を見てから言えって言うんだ。復興住宅だって全然、間に合ってないだろう。オリンピックの準備で職人も材料も足りないし、値段も上がってしまってさ。オリンピックなんて……たったの四年も待てないのかと思うね」
いずれにせよ、来年3月にMさん一家は大きな決断を迫られることになる。富岡に帰るのか帰らないのか、勿来を終の棲家にするのかしないのか。
「俺たちは親から何にも貰わないで、箸一本から始めた夫婦だからな。富岡になん十年も住んで、2回も家を建て替えたんだ……」
Mさんの立ち位置には、被害者と加害者の両面がある。しかし、Mさんはこう言うのである。
「一番かわいそうなのは、地元採用の東電の社員だよ。社員は避難しても補償金貰えないんだよ。それだと女房、子供を抱えて生きていけないからさ、泣く泣く東電をやめた人もいるよ。地元採用の社員がやめて現場を知らない人がたくさん入ってきたら、例の汚染水のタンクが漏ったりするんだ。だって、フランジの締め方ひとつ知らない素人ばっかりなんだからさ。昔の仲間に会うと、『みっともねーなー』って話になるな」
Mさんの言葉からは、東電傘下の企業で働いていたプライド、職人としてのプライドは感じられても、東電が事故を起こしたことへの怒りはまったく感じられない。避難民としても、それほど激しい怒りを持っているわけではなかった。菅総理や国への憤りの言葉はあったが、事故原因をあくまでも究明したいとか、故郷を完全に元の状態にして返してほしいというような、激越な言葉はなかった。
Mさんの年齢もあると思うが、言葉の端々から響いてくるのは、手厚い補償を貰っていることに対する納得感と、諦めの気持ちであった。
避難指示の解除に五年もの月日がかかったことで、おそらく富岡町から避難した人の多くが、Mさんのように避難先で新たな生活を始めてしまっている。子育て世代は子どもの学校の問題があるから、なおさらその傾向が強いだろう。
では、もっと早く避難が解除されていたら、町民の多くが町に戻ったのだろうか? 放射能に関して無知な人々の「無用の恐れ」が、避難解除を遅らせたのだろうか? 政治家がもっと強いリーダーシップを発揮して帰還を推進すればよかったのだろうか?
わたしにはまだよく分からないが、事故原因の解明や責任の所在の追及、そして放射能の影響に対する科学的な評価の確定といったことによって避難者を納得させるのではなく、「金と時間」によって少しずつ人心を宥めていくやり方に、私は漠然とだけれど“日本的なもの”を感じた。
取材の終わりに、Mさんが自作の川柳を書きつけたノートを見せてくれた。
・ふるさとと 今の住処を はかりかね
・わがいのち つきてもまだ ひなんかな
・ひとしれず きえさるのみか ろうじんは
![]()
![]()
![]()
▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。