グローバル化とグローバル・ジハードがうねりとなって交錯するところへ、イギリスのEU離脱やアメリカのトランプ政権発足という潮流がなだれこみ、世界はガラガラと音を立てて地殻変動を起こしている。
そんななか、日本人は経済、外交、エネルギー問題にどういう視座を持つべきだろうか。中東にどう向き合うべきだろうか。
日本を代表する論客の一人が、「寺島流」フィールドワークともいうべき独自の視点から、国内外の経済、政治、外交、エネルギー政策、宗教に斬り込んだのが、本書である。
筑豊の炭鉱での「原体験」
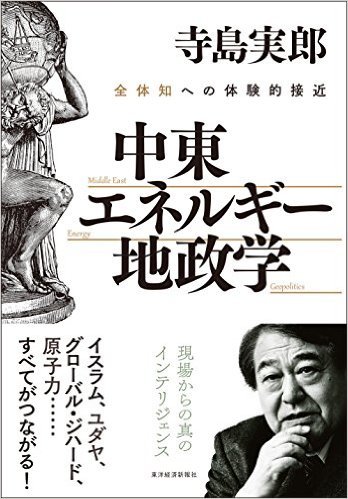
冒頭。敗戦まもない1947年に北海道・沼田町の炭鉱町で著者が生まれたところから、著者のエネルギー問題、そして中東との「運命的な縁」が始まる。
やがて、筑豊の炭鉱に一家で移り住んだ著者は、初めて「社会問題」を意識することになる。そこには、土門拳の写真集『筑豊のこどもたち』から、「弁当を持っていない子」と題する1枚が掲載されている。
<私はこの写真を見ると今でも胸が締め付けられる。出版されたのは1960年だが、そこに切り取られた光景は、私が目にしたそれとまったく同じものだからだ。父が大手企業の安定した管理職という「恵まれた子ども」だった私は、毎日弁当を持って学校に通ったが、教室には弁当の時間に皆が昼飯を食べているのを横目で見ながら、じっと本を読んでいる同級生が確かにいた。>
「黒いダイヤ」ともてはやされ、戦後は復興の柱として活況を呈した石炭産業だったが、早くも50年代後半には陰りが兆していた。
石炭から石油へ、「エネルギー流体革命」の荒波にさらされた筑豊の炭鉱の「原体験」は、著者の眼を社会に向けた「最初の窓」となったという。
労務担当だった著者の父は、従業員の再就職先を探すため東奔西走した。「花形産業の残酷なまでの末路に、強烈なインパクトを受けた」著者は、石油危機の73年、三井物産に入社した。

















