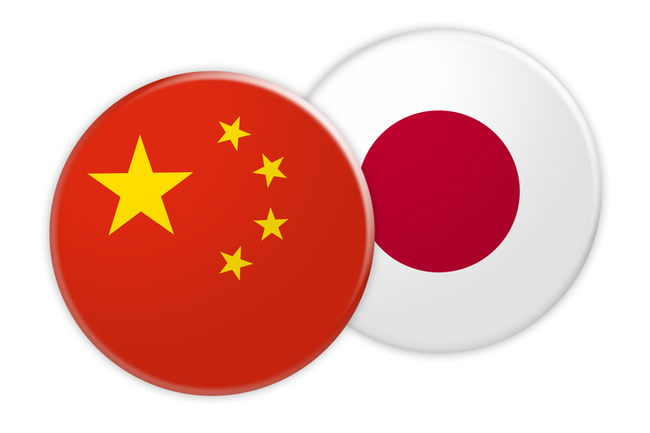
関税の掛け合いに端を発した米中貿易戦争は、5G情報通信システムを軸にした将来の世界覇権をめぐる新たな冷戦へとエスカレートの様相を見せ、先行きは不透明なまま。強気一辺倒のトランプ大統領が仕掛ける予測不能な“ツイッター政治”に、世界は振り回されるばかり。
ポンぺオ国務長官とボルトン国家安全保障問題担当大統領補佐官の2人の対中強硬派が脇を固めた政権が打ち出す中国警戒論は、いまや与野党を問わずワシントンの共通認識になっているとの報道もあるが、こういった対中強硬姿勢はいつまで続くのか。
歴史を振り返ってみるなら、アメリカは中国に対し基本的には好意的、いや立ち遅れた中国を教え導くのが使命であるかのように振る舞ってきた。その姿をヴェトナム戦争報道で名を馳せたジャーナリストのD・ハルバースタムは、「多くのアメリカ人の心のなかに存在した中国は、アメリカとアメリカ人を愛し、何よりもアメリカ人のようでありたいと願う礼儀正しい従順な農民たちが満ちあふれる、幻想のなかの国だった。・・・多くのアメリカ人は中国と中国人を愛し(理解し)ているだけでなく、中国人をアメリカ化するのが義務だと信じていた」(『朝鮮戦争(上下)』文春文庫 2012年)と記している。
「仏教をテコ」に中国進出を目論んだ日本
19世紀半ば以降、大量のキリスト教宣教師が中国各地に送り込まれた。信仰の力で「中国人をアメリカ化する」という「義務」を果たそうというのだ。もちろん、その根底には中国における膨大な富を確保しようという狙いがあった。中国を舞台にした西欧列強による「大競争」に遅れてはならじ、である。
キリスト教宣教師を先兵にした西欧列強の動きを横目に、日本では仏教をテコに中国進出を目指そうという動きが起こる。その先頭に立ったのが、浄土真宗本願寺派第22代法主の鏡如上人こと大谷光瑞(明治9=1876年~昭和23=1948年)だった。
彼は8人の随行員と共に明治32(1899)年1月19日に神戸を発ち、上海、香港、広東、上海、杭州、南京、漢口、北京を周り、天津を経て同年5月3日には門徒の「雲霞の如き出迎の中馬車にて御機嫌美はしく御帰山」している。
出発を前にした大谷法主は、門徒に向けて「御親諭」を示し、旅行の目的――今回の清国巡遊は物見遊山などではなく、同じく仏教を信仰する清国が西欧列強によって分割支配された場合、その影響は我が国にも及ぶ。だから立ち遅れた清国を啓発・再興し文明化させることで西欧列強の野望を打ち砕く。それは隣国としては当然のことであり、また我が国の自衛のためにも必要だ――を説いた。
清国の仏教は「現今殆ど衰残の極に達し」、「四億の民衆」は「地底に埋没し」「飢渇の境に彷徨」している。他のアジアの仏教国に目を転ずれば、「カンボヂヤ、安南、緬甸の諸王国前後相次滅亡に就き、其他土耳古、暹羅、朝鮮、支那或は独立国たり或は半独立国たりと云へども、其実は皆半滅亡の悲境に瀕する」ばかりだ。いわばアジアの仏教国において「純粋に名実共に独立国の面目を完全に保有するは独り我日本帝国あるのみ」。であればこそ、「我の責任此に至りて亦重大且大ならずや」ということになる。
こうして日本の仏教徒こそが「重大且大」なる責任を負うべきではあるが、「我国仏教徒の特に注意すべき点は、此の如く頻々滅亡に就く諸国は大概仏教国にして其民は多く仏教徒」ではあるが、「之に反して其征服国者即ち其勝利者は、悉く耶蘇教国にして其れ民皆耶蘇教徒なる事」だ。
清国で勝利者として振る舞っている耶蘇教徒の姿に、一行は上海で出会うことになる。

















