米国・イランの全面衝突は回避する動きとなり、原油価格も落ち着きを取り戻した。しかし、両国の激しい対立構造は全く不変のまま残存しており、今後の中東情勢や原油価格の動きに予断は全く許されない。
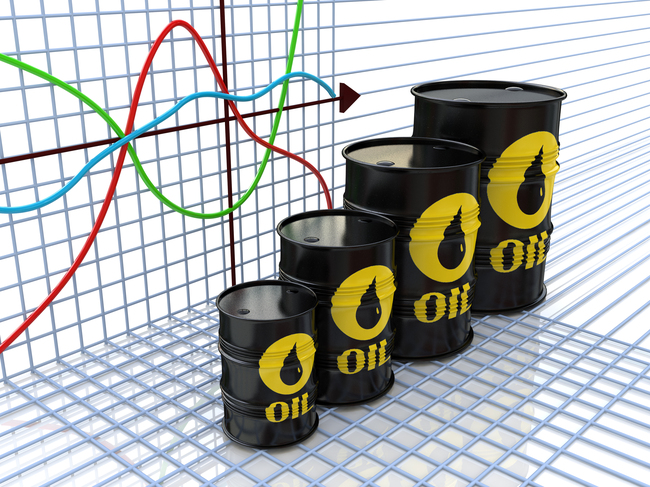
2020年の幕開けは、米国とイランの軍事衝突リスクの高まりで、大揺れ・波乱のスタートとなった。全面衝突や戦争リスクの懸念が高まり、世界経済への影響や石油供給途絶、原油価格高騰のリスクに世界が身構えることとなった。
きっかけは1月3日の米国によるイラン革命防衛隊の精鋭「コッズ部隊」のソレイマニ司令官のイラク国内における殺害であった。米国は、米国人へのテロの差し迫ったリスクを取り除くために決行した軍事作戦であると主張したが、国民的英雄である同司令官を殺害されたイランでは、指導者から国民一般に至るまで米国を激しく非難し、米国への報復が声高に叫ばれた。一方、米国は、仮に報復が実施されれば強力に対抗する、と強く牽制し、報復の応酬とエスカレーションによる全面衝突発生の可能性が高まった。戦争リスク懸念がこれまで以上に高まり、中東情勢は一気に緊迫の度合いを高めたのである。
1月8日、イランはイラク国内の米軍基地2か所を弾道ミサイルで攻撃した。この「報復」に、米国がどう反応するかを世界は固唾を飲んで見守った。その決断が注目される中、トランプ大統領は、米国人の死傷者は無かったこととして、軍事力ではなく、新たな経済制裁強化で対抗する方針を打ち出し、全面衝突・戦争は、とりあえず回避される形となった。
大統領選挙を控えるトランプ大統領も、軍事力に彼我の差がある中で全面衝突となれば体制安定が脅かされかねないイランも、ともに本音では全面衝突は避けたいところであった。報復の拳を振り上げたイランとしては、先述の弾道ミサイル攻撃実施は、国内向けに報復実施を示しつつ、米国による軍事報復を回避しうるギリギリの線を、熟慮に熟慮を重ねて戦略的に選択し、実行に移したものとの見方も示されている。
軍事衝突リスクとそれによる石油供給途絶発生への思惑から、原油価格は大きく動いた。1月6日には指標原油ブレントの先物価格が一時は70ドルを突破し、事態の推移によってはさらなる上昇も不可避、との懸念が市場に広まった。全面衝突と大規模石油供給途絶の場合には100ドル超えの可能性もゼロではない、との見方さえ示された。
しかし、結果的には、全面衝突と戦争を回避する動きとなり、状況はとりあえず沈静化した。原油価格も一時の高値圏から下落し、1月10日時点ではブレントは65ドル程度まで値戻ししている。しかし、とりあえずの落ち着きを取り戻したとはいえ、今後の中東情勢や原油価格の動きに予断は全く許されない。
原油価格の動きについては、今日の価格決定を主導するのが、ニューヨークやロンドンにおける先物市場である点にも留意する必要がある。そこでは、①石油需給ファンダメンタルズ、②金融要因、③地政学リスク、の3つが相互に影響しながら日々の価格が決まる。別の見方をすれば、これら3つに関する取引関係者の「思惑」「先読み」が価格を動かしていくのである。
例えば、今回の価格上昇局面では、需給ファンダメンタルズに関する思惑が基底要因となったところに、地政学リスクが重なった影響を見ることができる。原油価格は昨年末にかけて緩やかな上昇基調にあったが、その原因は、「OPECプラス」産油国による協調減産強化、米中貿易協議の第1段階合意発表、世界経済リスク後退等で、2020年の国際石油需給が引き締まる方向に向かうとの期待があった。また、世界経済リスク感の後退で、「リスクオン」となった市場にマネーが流入する金融要因もあった。ここに、中東情勢緊迫による地政学リスクが加わり、価格上昇が加速化した側面がある。
地政学リスクは、基本的に常に重要な問題であるが、その効き方は①②要因の影響との兼ね合いもある。石油市場がジャブジャブに緩和しているときは、地政学リスクがあっても市場は反応しにくい。今回は、その意味で市場の地合いが地政学リスクに反応しやすい状況になっており、そこに、米国・イランの全面衝突の可能性という、従来よりもはるかに深刻なリスクが影響したとも考えられるのである。

















