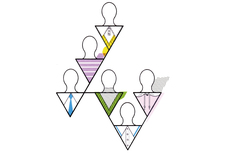日本シリーズの〝巨人2年連続4連敗ショック〟が、球界とファンの間でいまだに尾を引いている。巨人OB評論家から原辰徳監督に対する批判が続出している一方で、「この先の数年間、いや、ひょっとしたら10年以上、セ・リーグはパ・リーグに勝てないだろう」などと悲観しているファンも少なくない。

しかし、本当に、セ・リーグはまったくパ・リーグに歯が立たなくなったのか。何も手の打ちようがないのか。今年2月に他界した名監督・野村克也氏は生前、よくこう言っていた。
「野球とは、弱者が強者を食えるスポーツや。だから面白い。長丁場のレギュラーシーズンはチーム力の差が物を言うが、日本シリーズやクライマックスシリーズのような短期決戦は戦略次第で勝機を見出すこともできる」
確かに、セ・パ両リーグの実力格差はいまや歴然。実際、巨人が2勝4敗で日本ハムをくだした2012年以降、セはパに一度も勝っていない。とくに、相手がソフトバンクとなると、18年には広島が1勝1引き分け4敗、15年はヤクルト、14年は阪神がともに1勝4敗と、ほぼ一方的に敗れている。
しかし、そうした中で、ひょっとしたらソフトバンクに勝てるのでは、と一縷の望みを抱かせたチームもあった。17年に2勝4敗と、12年以降で最も健闘したDeNAである。
第1~3戦では巨人と同じように3連敗しながら、第4、5戦と2連勝。最終的には第6戦で敗退したとはいえ、4敗のうち3敗は1点差(第2戦3-4、第3戦2-3、第6戦3-4)と、ソフトバンクを相手に予想以上の接戦を展開して見せたのだ。
DeNAがこれほど善戦した最大の要因は、何と言っても先発投手の頭脳的かつ粘り強い投球にあった。
勝ち星こそ逃したものの、2試合に先発した今永昇太は、第2戦が6回で5安打1失点10奪三振。第6戦が7回3分の0で2安打2失点11奪三振。ちなみに、日本シリーズでの2試合連続2桁奪三振は、長い球史においても、この年の今永と07年の日本ハム・ダルビッシュ有(現大リーグ・カブス)のふたりしか記録していない。
今永の真っ直ぐの最高速度は151㎞だが、パ・リーグのパワーピッチャーのように球威とスピードで勝負したわけではなかった。第2戦ではチェンジアップを多投してソフトバンクの打者の意表を突いたかと思うと、第6戦ではそのチェンジアップを狙われると見て封印し、徹底して真っ直ぐで押した。
さらに、その真っ直ぐにタイミングを合わされそうになったら、今度はカットボール系のスライダーも織り交ぜている。まさに緩急自在の配球に、ソフトバンクの打者はタイミングを狂わされ、三振と内野ゴロの山を築き続けた。
そんな今永以上の快投を披露したのが、第4戦に先発したこの年のドラフト1位新人・浜口遙大である。チームが3連敗してあとがない土壇場、しかも本拠地の横浜スタジアムでの日本シリーズ初登板。これ以上ないほどプレッシャーのかかる舞台で、8回1死まで無安打無得点を続け、7回3分の2を2安打無失点に抑えたのだ。
浜口の真っ直ぐの平均速度はせいぜい140㎞台後半どまりで、パワーピッチャーの代表格、ソフトバンク・千賀滉大のような剛速球は持ち合わせていない。そこで、勝負どころでフォークとチェンジアップを使い、ソフトバンク打線を翻弄。「シーズン中投げたことのないスライダーも投げた」という。
スコアラーから渡されたデータにない配球で攻められたソフトバンクの打者は、八回1死から鶴岡慎也が右中間へ二塁打を打つまで沈黙させられたまま。記者席で取材していて、胸のすくような快刀乱麻の投球だった。
今永と浜口の好投の裏側には当然、DeNAのスコアラーたちが事前に収集したデータがある。そのデータを最大限に生かそうとした捕手・戸柱恭孝、髙城俊人のリードと配球の巧みさも見逃せない。
この年のDeNAに比べると、昨年と今年の巨人首脳陣とバッテリーには、いかにも工夫や対策が足りなかった。セ・パ両リーグ間にどれほど実力格差があろうと、昨年対戦した同じチームに4試合で計26点も取られるという体たらくは、野村克也氏の言う短期決戦ならではの「戦略」が決定的に欠けていた、と言わざるを得ない。
なお、セ・パの実力格差が声高に叫ばれているのは、何も昨年や今年から始まったことではない。古くはノムさんが南海(現ソフトバンク)の現役選手だった時代から、球界には「人気のセ、実力のパ」という〝格言〟があった。
1990年の日本シリーズでは、当時「王者」と呼ばれた黄金時代の西武に巨人が4連敗。セのレギュラーシーズンでは88勝、2位とのゲーム差22という記録的な独走優勝の末の完敗だったからショックは甚大だった。当時は「球界の盟主交代を象徴するシリーズ」とも言われたものである。
それから早くも1年後、4連敗ショックを払拭したのが、91年の日本シリーズで西武と激突した広島だ。ファンも評論家も西武圧勝と予想していた中、広島は先に3勝して王手をかけ、日本一に手がかかるところまで迫ったのだ。
この広島の大善戦も、やはりシリーズ前の入念な準備の賜物だった。とくに、クリーンアップの〝AKD〟秋山幸二、清原和博、オレステス・デストラーデをはじめとする西武の強力打線を封じ込めるため、首脳陣はバッテリーと守備陣に状況に応じた配球とシフトを徹底させた。このときは、一部コーチが秘かにダイエー(現ソフトバンク)のスコアラーから入手していた詳細なデータが役に立ったという。
本拠地・旧広島市民球場での第5戦で3勝目を挙げたとき、私が取材した主力選手たちはのちに「勝ったと思った」と口をそろえている。が、西武球場に移ってからの第6戦で、1-1と同点だった五回、勝ちを焦った山本浩二監督が、翌日の第7戦に先発予定だった川口和久を投入。これが裏目に出た。
川口は第5戦でシリーズ2勝目を挙げて中1日のリリーフ登板で、本来の投球ができるはずもない。代打・鈴木康友に勝ち越しの2点タイムリーヒットを打たれて、流れは一挙に西武へ傾く。結果、この第6、7戦と2連敗してしまったのだ。
実はこのとき、広島ベンチでは、大下剛史ヘッドコーチが川口投入に反対し、山本監督と押し問答をしていたという。のちにそんな裏事情を知った森監督は、「もし大下の意見が通っていたらこっちが負けていただろう」と漏らした。
結果はともかく、王者・西武と言えども、恐るるに足らず。広島の大善戦を契機に、セ・リーグ球団にはそんな認識が広まったように、私は感じた。