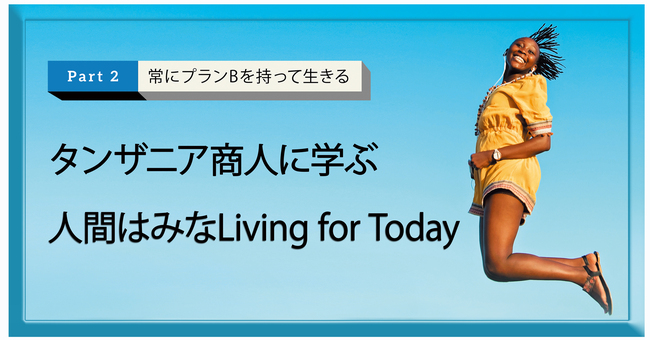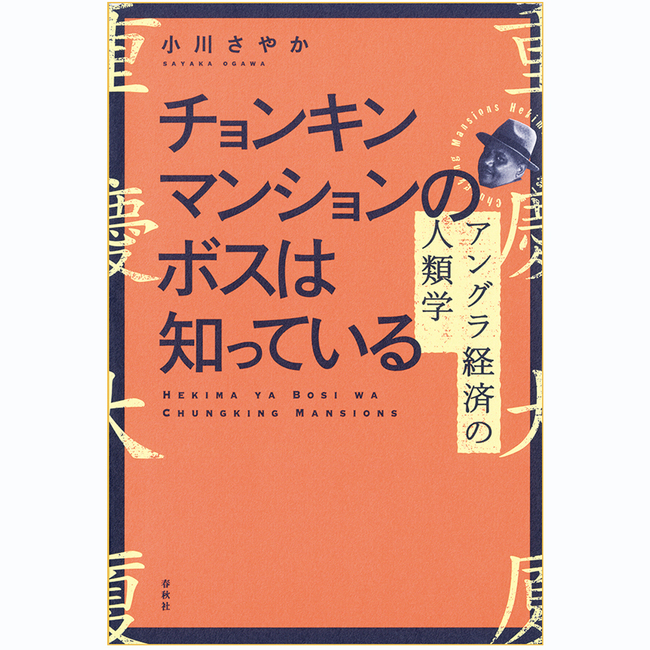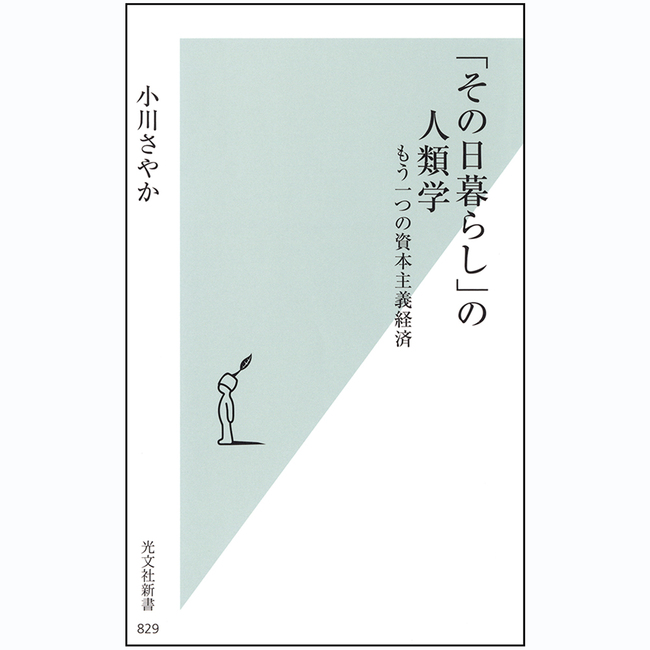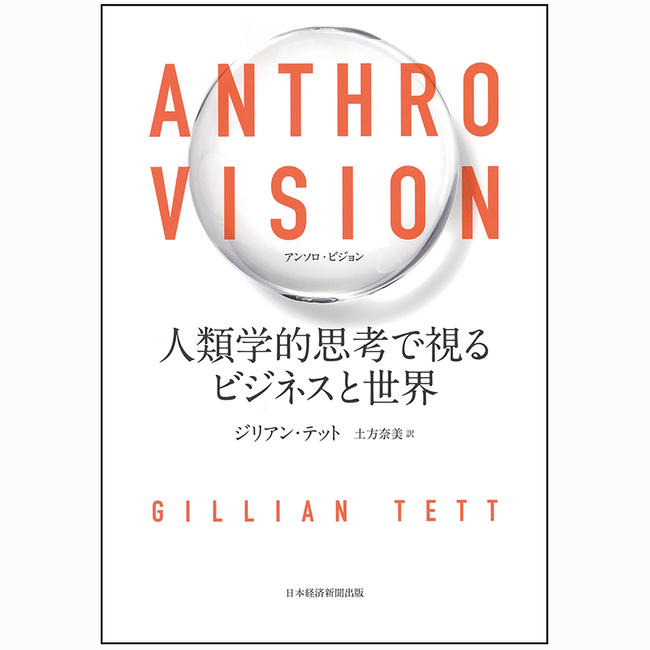「Wedge」2022年6月号に掲載されている特集「現状維持は最大の経営リスク 常識という殻を破ろう」記事の内容を一部、限定公開いたします。全文は、末尾のリンク先(Wedge Online Premium)にてご購入ください。
不安定な暮らしでも前向きに、不安定だからこそプランBを持つタンザニアの商人たち。人類学の視点から、今の日本人や日本社会に必要なマインドセットを考える。
聞き手・構成 編集部(大城慶吾、友森敏雄)
聞き手・構成 編集部(大城慶吾、友森敏雄)
タンザニアの零細商人(マチンガ)の世界に飛び込んで自らも古着を売り歩き、インフォーマル(統計に載らない)経済の実像を浮かび上がらせた『「その日暮らし」の人類学』(光文社新書)。そして、タンザニアの交易人たちの香港や広州での動きをまとめた『チョンキンマンションのボスは知っている』(春秋社)。彼らは不安定だからこそ仲間内でちょっとした貸し借りを繰り返すことで困ったときには互いに助け合う。文化人類学者の立命館大学・小川さやか教授に、現在の日本社会を覆う「違和感」や「閉塞感」打開のヒントを聞いた。
なぜ安定よりも
不安定を選ぶのか?
人類学の博士号を持つフィナンシャル・タイムズ(FT)米国版編集長を務めたジリアン・テット氏の『ANTHRO VISION 人類学的思考で視るビジネスと世界』(日本経済新聞出版)では、人類学者を採用する企業の動機について紹介している。
あるべき未来像が掴みにくくなる中で人類学の調査方法である「参与観察(詳細は後述)」や、異文化を通じて自文化を見つめなおすという「アウトキャスティング(外側からの予測)」の思考法により、企業は自社の製品開発や組織改革などに生かしているようだ。