20世紀初頭、英独間で熾烈な建艦競争が生じた。
ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世は海軍力の増強によって英国に追いつくことを公言し、対する英国も追いつかれまいと戦艦を建造し続け、当時の英国民を不安に陥れた。そしてその不安に火をつけたのが、英国人ジャーナリスト、ウィリアム・ル・キューが1906年に発表した架空戦記、『1910年の侵攻』である。
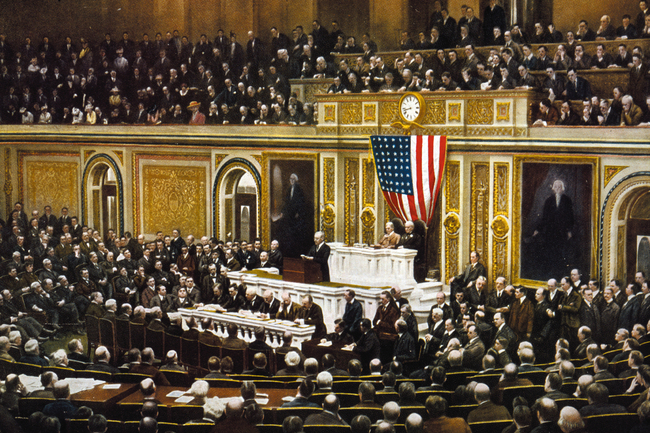
本作は1910年という近い将来に、ドイツ軍が英国本土に侵攻してくるという筋書きであり、その侵攻ルートまでが詳細に描かれていた。大衆紙『デイリー・メール』紙上で連載されており、同紙は販売戦略のためにドイツ軍の脅威を過度に煽ったのである。
さらにル・キューは09年にも『ドイツ皇帝のスパイたち』と題した小説で、既に5万人を超えるドイツ人スパイが英国内で暗躍していることをほのめかした。もちろんこの数字には何の根拠もなかったが、当時の英国人読者はこれを深刻に受け止め、政府に対応を求めることになる。
架空戦記で生まれた
世界初の常設情報機関
この小説の影響は一般の英国民だけではなく、陸軍省作戦部長、ジョン・スペンサー・ユーアート中将やその同僚、ジェームズ・エドモンズ大佐など軍の中枢にも及んでいたのである。そこでユーアート作戦部長を中心に検討が進められ、09年10月、英国内のドイツ人スパイを摘発する保安局(後のMI5)とドイツの軍拡についての情報を収集する秘密活動局(後のMI6)が設置されることになる。これが世界で初となる常設の情報機関の誕生であった。
しかしその後勃発した第一次世界大戦において、誕生したばかりの秘密活動局の活動は低調であった。組織の長に任命された海軍士官、マンスフィールド・カミング中佐も情報勤務の経験がなく、組織としてもノウハウを有していなかったためである。
戦争においては軍事情報が必要となるが、それは陸海軍の情報部の領域であり、秘密活動局の出番はそれほどなかったのである。むしろ英国の政官街で新設の組織が潰されないようにすることで精一杯だったが、カミングは政治的立ち回りには秀でており、何とか組織を維持することに成功し、初代長官としての面目躍如を果たした。
カミングは書類にサインする際、海軍由来の緑のインクで自らのイニシャルである「C」と記していたが、それ以降の長官も彼に敬意を表して「C」とサインするようになり、この慣習は現代にも受け継がれている。MI6におけるカミングの評価をよく表しているといえよう。
第一次世界大戦で活躍したのは英海軍の情報機関であった。戦争が始まると英海軍情報部長ヘンリー・オリバー大将は、物理学者ヘンリー・ユーイング博士ら、在野の数学者、言語学者を集めて海軍省本部の40号室に暗号解読組織を立ち上げた。これは後に「40号室」と呼ばれるようになる。

















