19世紀初頭のナポレオン戦争後しばらくの間、平和な時期が続いたが、後半以降は多くの戦争が勃発する。特に1853年のクリミア戦争と61年の米国南北戦争はかなり規模が大きく、長期間の戦いとなった。これらの戦争においては、当時の最新技術である電信による情報伝達が戦争指導のあり方に大きな影響を与えたのである。
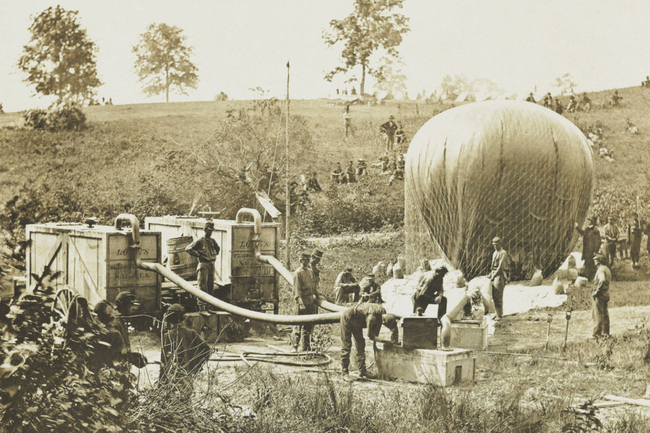
ロシア軍が現在のモルドバ、ルーマニアに侵攻する形で始まったクリミア戦争は、当初は地域紛争の様相を呈していた。しかし53年11月に黒海南岸の港湾都市シノープで、トルコ海軍がロシア海軍に大敗を喫すると、この海戦の様子が「シノープの虐殺」として、英仏の新聞で伝えられた。既に欧州の電信網は中東にまで達しており、クリミアの戦場の様子が毎日刻々と伝えられていたのである。この報道によって英仏の世論は反ロシア一色となり、英仏政府はクリミア戦争への参戦を余儀なくされている。
倒閣の主犯は
メディアだった?
クリミア戦争では、英仏の政治家や軍人が、初めて新聞というメディアに頼るようになった。それまでは政府機関による報告が主な情報源であったが、この時代には毎朝の新聞報道の方が情報を速く伝えるようになっていたのである。
ただし、新聞報道はロシア側でも読まれており、クリミアに派遣されていた英陸軍総司令官フィッツロイ・サマセット大将は、ロシアは『タイムズ』の記事のおかげでスパイを放つ必要もなく、あっという間に情報が伝わってしまう、と不平を述べていた。
実際、『タイムズ』はロシア皇帝ニコライ1世も目を通しており、英仏の宣戦布告の最後通牒を受け取るよりも先に、同紙によってそのことを知ったという。そして連日のように英軍の苦戦ぶりが各紙で報じられると英国の世論は政府の戦争指導ぶりに苛立ちを強め、遂に当時のアバディーン内閣は解散を余儀なくされる。当時の与党は倒閣の主犯を『タイムズ』紙の従軍記者、ウィリアム・ハワード・ラッセルだと語気を強めた。
クリミアで英軍が苦戦した根本的な問題は、サマセット将軍が現地ロシア軍の情報どころか、地図さえない状況下で、作戦指導を行わざるを得なかった点だろう。戦場で鹵獲したロシア語の地図は読めないので、まず翻訳から行うありさまであった。その稚拙な戦いぶりから、かのマルクスは「ロバ(将軍)に指揮されるライオンたち(英兵)」とまで揶揄している。
それでも戦争は英仏連合軍の辛勝に終わった。これはロシアの軍事・インテリジェンスの制度が、前近代的なものにとどまっていたためであり、戦争中に皇帝となったアレクサンダー2世は、同分野での改革を断行している。インテリジェンス分野では、戦争終結後にロンドンやパリ、ウィーンといった都市で、ロシアの駐在武官に皇帝自ら情報収集の強化を命じるほどであった。当時、ロンドンに派遣されていたのは、後にロシアの内務大臣となる、弱冠24歳のニコライ・イグナチェフであった。

















