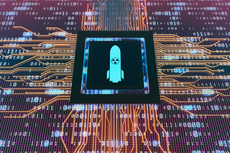「絶対的貧困」の過酷すぎる現実
世界銀行は、2022年9月に1日「2.15米ドル」(約320円)を「絶対的貧困ライン」とし、この1日2.15米ドル以下で生活している人々を「絶対的貧困」と定義しました。
なお、絶対的貧困ラインは、1991年に最貧国の6カ国を調査して算出され、初めて設定された当初は1米ドルでした。その後、物価上昇等を理由に修正され、08年に1.25米ドル、15年に1.9米ドル、そして24年現在は2.15米ドルとなっています。
これが貧困の世界的な水準です。世界の人口は約80億人とされていますが、現在では1日2.15米ドル以下で暮らす人々が、約8%いるとされています。命を維持するのも危ぶまれる絶対的貧困は、アフリカなどの途上国で見られる飢餓(starvation)のような状態であり、日本のような先進国で目にすることはほとんどありません。
『スラムドッグ$ミリオネア』*2という映画があります。アカデミー賞8冠を受賞した世界的な名作です。インド南部の大都市ムンバイ(ボンベイ)*3にあるスラム*4で、極限状態の生活を強いられていた主人公・ジャマールは、インドの国民的クイズ番組「クイズ$ミリオネア」に出演するチャンスを手にします。
この作品では、絶対的貧困状態にある人々の現実が生々しく描かれています。ムンバイのスラムは世界一荒廃していると言われており、ジャマールの育った環境は想像以上に過酷なものでした。なかには物乞いをするために少しでも同情が集まるよう、失明させられたり手足を折られたりといった衝撃的な場面も描かれています。
実際、必要最低限の生活水準を維持するため、幼い子供が過酷な労働環境に身を置かれるのは珍しいことではありません。食べ物を買うことをはじめとして、とにかく生きるためにおカネを稼ぐことは、彼らにとって喫緊の課題なのです。
*2 2008年公開のイギリス映画、ダニー・ボイル監督。実在する国民的クイズ番組に出場した青年の生い立ちを通じてインド社会の現実を描いています。
*3 デリー・ニューデリーと並ぶインド最大規模の大都市。なお、「ボンベイ」は英植民時代の名称。映画産業が盛んで、ハリウッドにちなんで「ボリウッド」とも言われています。
*4 極貧層が居住する過密化した地区。日本では1960年代になくなったとされています。
「相対的貧困」の支援が難しい理由
一方で「相対的貧困」は、可処分所得が中央値の半分以下である場合を指します。つまり、その国の大多数よりも貧しい状態にあるということです。
まさに相対的な比率なのですが、相対的貧困は絶対的貧困に比べて可視化しづらく、支援が難しいと言われています。そのため、行政などによる支援がなされず、貧困が世代間で連鎖し、貧困状態が固定化してしまうという問題が考えられます。
たとえば、貧しい家庭に生まれた子供は、十分な教育や医療を受けられず、大人になっても低賃金で不安定な職にしか就けないということがあります。すると、その次の世代(子供)にも十分な教育や医療の機会が与えられず、知識や健康面でハンデを背負ってしまう確率が高まるのです。
なお、日本では厚生労働省*5が「相対的貧困」を算出しており、所得が「約130万円」(貧困線)以下の場合を相対的貧困状態と定め、相対的貧困率は約15%としています*6。つまり6人に1人が貧困状態にあり、なかでも母子家庭の割合が高いといった状況です。
*5 日本の行政機関のひとつ。「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指すために、健康、医療、福祉、労働など、国民生活の保障・向上を担っています。
*6 「国民生活基礎調査」(2021年)参照。