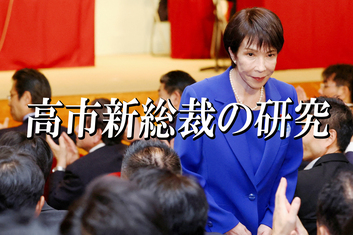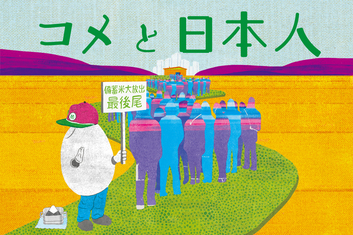自然保護への対応に腐心する国有林
それでは各地の自然保護活動に対して、国有林はどのような対応をしていたのか。その一例を見てみよう。
熊本営林局(現九州森林管理局)多良木営林署(現熊本南部森林管理署の一部)の事例で85年ごろである。球磨盆地東端の宮崎県境に立つ市房山(標高1721m)は球磨郡の最高峰で、盆地のどこからでも見え、信仰の山でもある。
この聖なる山は、実は花崗岩で風化が進んでいて崩れやすく、宮崎県側の民有林では皆伐後拡大造林して10年以上経っていたが、表層崩壊が至るところで起きた。崩壊地と植林地が市松模様になって無残な姿で、誰が見ても造林失敗と言わざるを得なかった。
熊本県側は上部が山頂まで国有林だった。ほとんどが天然林で伐採するような地形ではなく、伐採予定もなかった。ところがその下に70から80年生のスギの優良な人工林があって、伐採予定があった。これを知った地元の自然保護団体が、伐採によって土砂流出が起きて、市房ダムに流れ込むと反対運動を起こした。
確かに理屈は通っているのだが、現場は緩傾斜地で皆伐しても崩壊が起きるとは思えない箇所だった。保残区方式なので幅の広い保残区を設定するから、仮に崩壊しても土砂流出はくい止められる。
しかし、団体側は地元紙やテレビなどマスコミを動員して攻勢をかけてくる。当時は今と違って、一般市民の自然保護に対する意識は高く、マスコミもしっかり勉強していて、結構専門的な質問を飛ばしてくる。皆伐施業なんか現在の方がひどいなと思うことも多いが、社会的批判はすっかり下火になり、マスコミも林野庁の応援団かと思うくらい不勉強だ。
熊本営林局は傘下の営林署が40を超える大所帯なので、よほどのことがない限り対応は営林署にお任せである。営林署長は背負っているものが多い。
国有林伐採に期待しているのは、地元の製材所、チップ工場、九州に多い陶器の化粧箱を作っているモミツガ協同組合、それと伐採業者である。もちろんこれらの企業には地元住民が雇用されており、その家族もいる。関係企業には天下りのOBもいてうるさい。署員でさえ、署長の手腕を値踏みしているようなもので、どこまで味方かわからない。虎視眈々と署長のミスを狙っている労働組合までいるのだ。団体相手に卑屈にぺこぺこしていることは許されない。
結局、このような事案は技術的に解決するしかないのだ。皆伐を取りやめて非皆伐施業にする。間伐では間伐率が20%と低い。当時導入されたばかりの複層林施業(写真5)なら50%まで択伐できるので、事業的に有利である。そして、自然保護団体が大好きな広葉樹を樹下植栽することにした。
これで丸く収まった。択伐では、太いスギから選木して、伐採率は材積率なので伐採本数を少なくした。太いスギは事業効率が良いので費用軽減につながり、販売単価も高い。
もっとも太いスギは成長が良い分目粗(めあら)で、必ずしも品質が優れているとは限らない。複層林に保残したスギは細いから目が詰まっていて、今後の成長によってさらに品質が向上する可能性があった。結果的には対象となる森林全体を50%択伐することによって、保残区方式を超える伐採量となって、焼け太りしてしまった。
自然保護対応ではこのようにうまくいくことは稀かも知れない。得てして白か黒か、伐採か禁伐かになってしまうのだが、自然保護団体も営林署もウィンウィンであることが最良での裁きであろう。