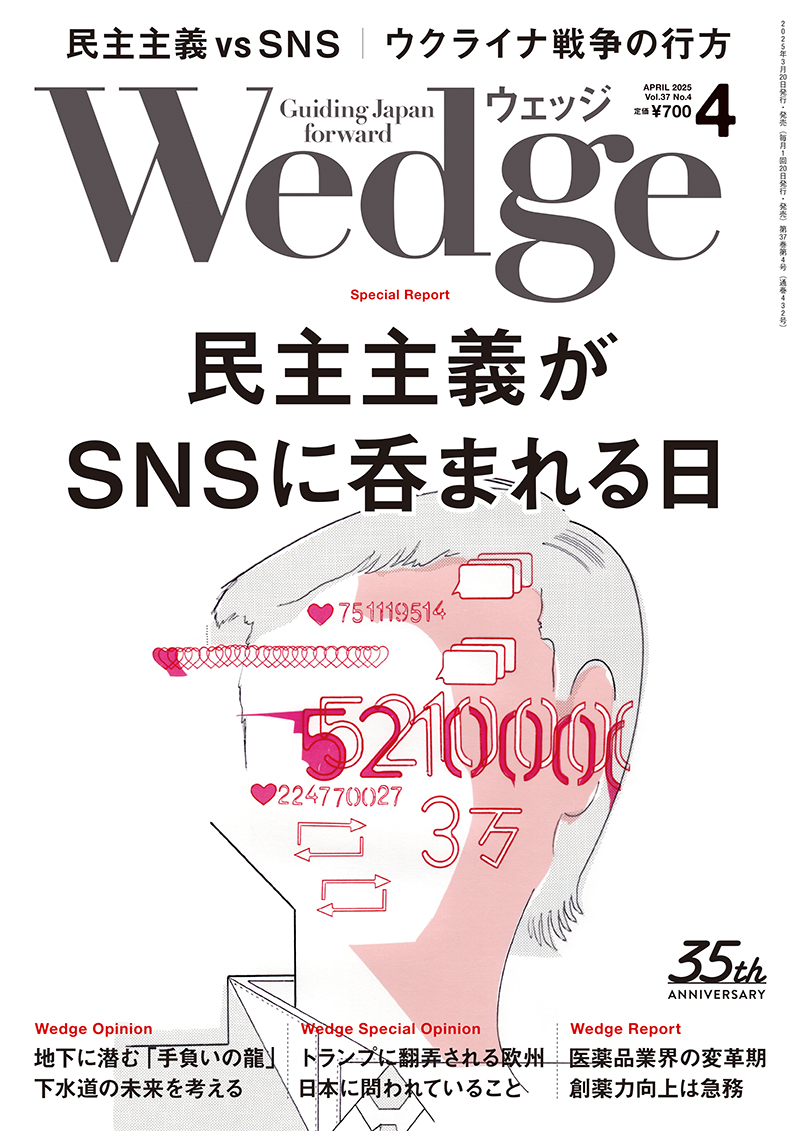大正後期に考案し、磨きを続ける
菊廼舎は、1890(明治23)年に銀座で創業し、冨貴寄は大正後期に考案されました。
「2代目が全国の銘菓を集めて瓶詰めにし、そこから『吹き寄せ』という言葉が生まれて縁起の良い字を当てました。現在の形の冨貴寄は1948年、3代目のときに出来上がりました。缶の柄も自ら描いたもので、今でも使用しています」
私は、包み紙に使用されている「宝づくし」の柄が大好きなのですが、これも3代目が考案したそうです。
「祖父に当たるのですが、戦地から帰還して、46年に閉めていたお店を再開させました。一度やるとなると、囲碁でも、お茶でも徹底的にやるスタイルで、絵についても有名な画家の元で修行させてもらっていたそうです。お洒落な人でもありました」
和を意識した干菓子を作るようになったのは120周年記念の時だったそうです。菊廼舎は今年の5月で135周年を迎えます。それに合わせた特製缶の作成も進められています。缶のデザインを新しくするために、缶の収集家の方からのアドバイスをもらうという力の入れようです。
「心やすらぐおいしいものを」というのが菊廼舎の社是になっています。
「4代目である私の父が作りました。季節感、空間、時間を大事にし、もらった人も、あげた人にも『良かった』と思えるものを作ろうという気持ちが込められています」
井田さんの名刺には「一級菓子製造技能士」という肩書が載っています。
「かつては経営面での仕事に注力していたのですが、職人も人手不足という時代になったことで、私も現場に立てるように取得した国家資格です。一級の技能試験は3時間半にも及びます。3回受けてやっと合格しました」
菊廼舎本店では、生菓子も作っています。お茶うけで頂いたマカダミアナッツをまぶした「揚げまんじゅう」はサクサクでとても美味しかったです。
菊廼舎は53年から東京駅にもお店を出しています。現在は、八重洲口東京ギフトパレットに出店しています。ここでも、冨貴寄はもちろん、揚げまんじゅうも買うことができます。本店に行く時間がない、というときにおススメです。