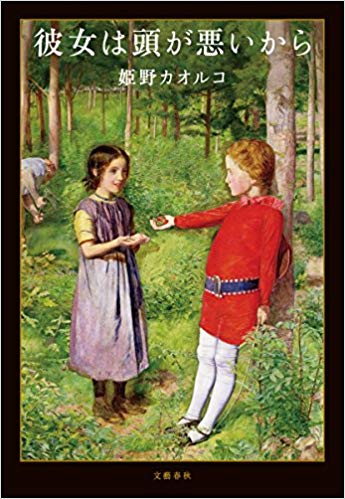性暴力の事件が大きく報道されるとき、被害者をバッシングする声は必ずつきまとう。『彼女は頭が悪いから』で描かれる集団強制わいせつ事件でも、被害者の女子大生は「勘違い女が東大生の人生を台無しにしようとしている」と、匿名の人々から非難される。
発売当初から話題を呼んだ同書について、著者の姫野カオルコさんに話を聞いた。12月に東京大学で行われたブックトークがネット上でも議論されたが、このインタビューはブックトークより前の11月14日に行ったもの。
1958年、滋賀県生まれ。青山学院大学卒業後、1990年にデビュー。『受難』(1997年)、『ツ、イ、ラ、ク』(2003年)、『リアル・シンデレラ』(2010年)など。『昭和の犬』で2014年に第150回直木賞を受賞。
ノンフィクションでは書けない性被害の実態
――私はここ3年ほど、性暴力の取材をしています。取材する中で思うのが、性被害の話はノンフィクションでは書けないことが多すぎるということです。被害者保護、あるいは加害者の人権の点からそのまま書けないことも多いし、また、性被害の実態と世の中の認識に乖離があるので、そのまま書いても複雑で伝わらないこともあります。「こんなの作り話でしょう?」と反応されてしまうこともある。もちろんノンフィクションにも意味はありますが、フィクションで、「これは作り物の話。どう読むかは読者に任せる」というかたちで世の中に性暴力の問題を問うのは意味があると思っていました。こういうものが読みたいと思っていたので、読めてうれしいです。
姫野:ありがとうございます。
――姫野さんは本書について「架空で非実用的な形態でなければ、書いている私や、私の隣人や知人や、同じ電車に乗り合わせたり病院の廊下ですれちがった人等々、生きて暮らしている人たちに在る真実は描出できないではないか」と書かれています。おっしゃる通りだと思います。
姫野:性暴力でなくても、介護の問題であっても受験体験や恋愛であっても、個人のことって人によって違います。人によって違うので、たとえばAさんのことを本当に正確に書いたら、それはAさんの話しか書けなくなってしまう。けれどもAさんとBさんとCさんとDさん、合わせてひとつの人間として設定して書くと、それはフィクションだけど広い範囲に普遍性を持って、より多くの人に伝えられたり、理解してもらったりすることができる。それがフィクションならではということだと思います。