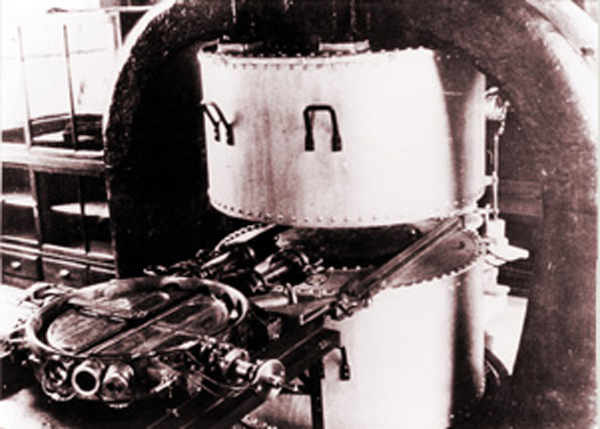日本学術会議をめぐる問題が解決の兆しが見えぬまま混迷を深めている。
菅義偉政権は2020年9月、6人の新会員の任命拒否で国民の関心を集めた上で、「日本学術会議のあり方を問う」と揺さぶりをかけた。だが、このやり方では同会議の現状に批判的だった元会長等も、立場上、学術会議を援護せざるを得ない。科学技術立国日本の崩壊を挙国一致で食い止めねばならない時機に、ことさらアカデミアと政府の対立を煽るのは百害あって一利なしだ。おまけに政府批判も学術会議批判も任命拒否問題を軸として回り始めた。
フレキシブルだった学術会議
筆者が訴えたいのは、国民の大多数から認められている自衛隊の存在や役割に、「社会全体では少数意見だが、ここ(=学術会議)では多数意見」との否定的な決議を続ける学術会議の浮世離れした実態である。早くも昭和30年代に自衛隊を認知し、役割分担を要請した創立期の学術会議は、もっとフレキシブルだった。現在も度々引用される学術会議の「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明」は、公的機関が自国の安全保障について述べることが許されなかった1950年(昭和25年)4月の第6回総会で行われたが、2か月後に朝鮮戦争が勃発する。
再軍備や単独・全面講和の論議が高まる翌年3月、「最近やかましく論ぜられている再軍備は、平和主義日本国の科学者の任務たる平和のための科学とその研究の自由を圧迫するに至る虞(おそれ)がある」に始まる「戦争から科学と人類をまもるための決議案」が第9回総会に再度提出される。趣旨は、「再軍備が強く論じられる今も、あの決議の精神が変わらないことを内外に表明したい」であった。ところが、「これは再軍備の是非を問うものではない」と提案者代表の新村猛名古屋大学教授(文学)が述べても、批判は再軍備問題に集中し、「学術会議は、この種の政治問題に踏み込むべきでない」と反対された。
我妻栄・東京大学教授(法学)などは「文章は独り歩きをする。この決議だけを読むと学術会議が再軍備に反対すると受け取られる」「戦争から科学を守るのに非武装、再軍備、外国依存と様々な選択があるが、学術会議が統一的見解を出せるものではないから、この種の声明は出すべきでない」と厳しく指摘した。そこで、「再軍備及び?再軍備等によって惹起される戦争から」を「再軍備等によって誘発される虞がある戦争」と弱い表現に改めたが、結局、賛成64、反対92、棄権5という大差で否決された。
同年10月、第11回総会で、この提案者たちは「講和条約調印に際しての声明案」と題し、「この従来の声明を再び確認し、その声明の実現を保障している日本国憲法を守るという固い決意を表明するものである」に終わる文を提案して再起を図る。代表の長田新・広島大学教授(教育学)は、「学術会議の姿勢を『良心の問題』として再確認したい。政治的な含みは無い」と説明したが、藤岡由夫・東京教育大学教授(物理学)は、「戦争を目的とする科学の研究云々は、一つの政治問題だ。学術会議は中立であるべきだ」と反対し、森戸辰男・広島大教授(経済学)は、「憲法を守るというのも一つの政治的な立場である」と批判した(杉山慈郎『「軍事研究」の戦後史』ミネルヴァ書房)。
4月に占領軍総司令官がマッカーサー元帥からリッジウエイ中将に代わって行き過ぎた占領政策の是正が進み、9月に講和条約も締結され、かなり自由に発言ができる空気になっていたせいで、3月の総会時よりも活発な討論が行われたと郷里の先輩、永井彰一郎・東京大学名誉教授(工業化学)は、筆者に述懐した。
我妻栄会員は、前年の宣言を疑うような見解さえ示す。「確かに1950年には『戦争を目的とする科学の研究には従わない』と宣言したが、国際情勢は変わり、今、朝鮮半島では戦争が起きている。いつか日本の科学者も勝つために働かないといけないことがあるかもしれない。その場合も『戦争を目的とする科学の研究』に絶対に従わないのか。あの声明は、そこまで禁じていないのではないか」。新声明の支持者側は、「憲法を守るのは国民の義務であり、また政治的な問題に学者としての立場を明らかにするのは悪いことではない」と反論する。そこで調停が入り、「絶対に(従わない)」と「憲法を守る云々」という字句を削除し、過去の声明を再確認するだけの修正案を提出したが、賛成56、反対93、棄権3で再び否決されている。1952年(昭和27年)10月の第13回総会にも同じ趣旨の声明案が提案されたが、挙手により賛成少数として採決に至らず3回目の否決となった。
当時の学術会議は、情勢変化を受け入れた。武力を背景とした近隣諸国の行動で「軍事的安全保障」を見る国民の目が更に変わっている今、現在の学術会議は何故変化を受け入れないのだろうか。
生い立ちへの正しい理解
ところが現在の同会議を非難する論客の多くが、同会議の生い立ちや果たしてきた役割を正しく理解していない。「日本学術会議、発足時から共産介入」(産経新聞、2020年11月18日)などと、同会議が最初から左翼団体の巣窟であったと記す報道も少なくないが、これも誤りだ。日本学術会議の前身は、1920年(大正9年)創設の「学術研究会議」である。パリに本部を置く万国学術研究会議の相方で、「国際極年」のように複数の学会や省庁が対応する国際科学事業では日本を代表して活躍した。終戦直後の1945年(昭和20年)9月にも原子爆弾災害調査研究特別委員会を設立し、学際的に活動した。
戦後、数多くの組織や制度が解体や改編にあい、その一環で学術研究会議も日本学術会議に改編された。それを連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指示によるものとする解説が多いが、実態は異なる。終戦の翌年、文部省を介さずに直接、日本の科学者との接触を図ろうとしたGHQ経済科学局は、全国の大学から20名程度の中堅学者を集めてサイエンス・リエゾン・グループ(SL)と称する委員会を結成させ、制度改革を討議させた。
日本人学者を使った間接統治と見ることもできるが、彼らも米軍御用学者ではなかった。委員長は、北大教授から東大教授となって4年目の茅誠司氏。東大理学部に設けた事務局の長は、元陸軍技術将校で物理学者の竹下俊雄氏。そして参加者の共通認識は、機能が重複する学士院、学術研究会議、学術振興会の3組織の改革にあった。一方、これについては早くも終戦直後の秋、山崎匡輔文部次官(筆者注・文部省記録によると、山崎氏は当時、正しくは科学教育局長で、次官昇任は1946年<昭和21年>1月である)が関係者を呼んで意見を求めたこと、参加者への土産は薩摩イモ2本だったことを、茅氏が書き残している。茅氏は学術研究会議の幹事でもあった(『思い出の人 茅誠司』<茅先生遺稿・追悼文集刊行会>)
文部省の求めで一足早く作られた3組織の代表による改革委員会では、長老学者で構成される学士院の発言力が強く、学術研究会議を解散して学士院に併合する案にまとまりかけた。だが、これをSL委員会経由で知ったGHQ経済科学局顧問のハリー・ケリー博士が不同意で、ご破算になる。文部省が収拾に乗り出し、全科学者の総意を代表する全国的機関として「学術体制刷新委員会」を作り、新たな体制を検討させる大事業に発展する。
沖縄のように軍政下にはなく、日本国政府による間接統治だったとはいえ、科学界や文部省を一喝できたケリー博士とは、どのような人物なのか。海軍兵学校の物理学教授であったが、第二次大戦勃発で母校マサチューセッツ工科大のレーダー開発チームに加わっている。昭和20年11月、米陸軍が、米統合参謀本部の指令に従い、理化学研究所のサイク
その任務は、教育・研究機関から廃棄すべき軍事器材とそうでない
ったが、仁科芳雄博士を公職追放から守るなど、戦後の学術復興に
東大教授も落選続出の第1回選挙
文部省のテコ入れも受けた学術体制刷新委員会は、文・法・経・理・工・農・医の7分野から15名ずつ、どの分野にも属さない3名を加えて108名の委員を全国から選び出し、1947年(昭和22年)8月、首相官邸で発会式を行う。科学者を代表して決意を述べたのは、湯川秀樹・京都大学教授だった。委員長は後に東京大学生産技術研究所長を務める兼重勘九郎・東京大学工学部教授で、茅氏は副委員長を務めた。
まだ列車旅行も宿泊も厳しい状況だったのに、刷新委員会は毎月の会合を開き、そこへSL、ML、EL、ALや、結成間もない進歩的文化人中心の民主主義科学者協会も新体制案を提出した。これらを討議した結果、学者の代表機関である学術会議、それと政府との中間の機関として科学技術行政協議会の創設が決定され、吉田茂内閣に答申した。「押し付け憲法」に比べると、十分審議されたと言える。
1948年(昭和23年)10月、日本学術会議法案が国会を通過し、12月には前記の7分野から30名ずつ、計210名の構成会員を選ぶ同会議の選挙が行われ、翌年1月に同会議は発足した。1948年(昭和23年)12月23日付の朝日新聞は「これまでの学術研究会議や学術振興会のメンバーに比べると、東大教授に意外な落選者が多く、その反面、私大や民間の学者の進出が目覚ましい」と報じている。嵯峨根遼吉・東大理学部教授も「意外な落選者」の1人である。長崎で、風船玉に縛り付けた米国の友人から嵯峨根氏宛ての手紙が投下され、それに「これは君も知る原子爆弾だ。すぐに終戦を上申せよ」と記されていたというほど、国際的に著名な原子核物理学者だった。
第4部(理学)の会員を見ると荒勝文策、茅誠司、坂田昌一、武谷三男、朝永振一郎、仁科芳雄、広尾徳太郎、伏見康治、藤岡由夫、三村剛昂、湯川秀樹各氏のような物理系が多いが、誰もが働き盛りで「長老」は見当たらず、共産党のスターもいない。「発足当時から共産党介入」というのは、せっかく会員に推挙された文系の3氏が直ちに代議士に転身したからだろうか。新派刑法学の先駆者でありながら九州帝大法学部教授の職を追われ検挙され、一切の研究活動や教職から締め出された風早八十二、同じく検挙歴のある経済学者の川崎巳三郎、検挙を契機に日本古代史研究家となった渡部義通の3氏は、所属の部会から学術会議会員に選ばれたが辞退。1949年(昭和24年)1月の第24回総選挙に共産党から立候補して当選する。
ただ、当時の国民が共産党を見る目は優しかった。18年も獄中に繋がれた徳田球一書記長、帝国大学教授でありながら投獄された河上肇氏や向坂逸郎氏は、転向しなかった殉教者として尊敬され、自衛軍の必要性を説いて「押し付け憲法」に抵抗する共産党は、一部のナショナリストの支持も集めた。前記の総選挙では35議席を獲得するに至るが、1951年(昭和26年)に山村工作隊などの武装闘争路線を採用したため支持を失い、翌年の第25回総選挙では候補者全員が落選して、党勢は衰退する。渡部氏は、共産党を離れた。
物理学会から推されて会員に当選した茅氏は、23年8月から文部省科学技術局長兼東大教授という身分であった。学術会議と文部省との円滑な関係維持に奮闘したが、「GHQ、特に民間情報教育局の強力な圧力の中で行政に当たった。経済科学局のケリー博士の支持で、辛うじて任に堪えた」と記している(『思い出の人 茅誠司』)。

写真右= 永田武・同IGY研究連絡委員会代表幹事。他の氏名は会議スタッフを務めた京大教官と大学院生