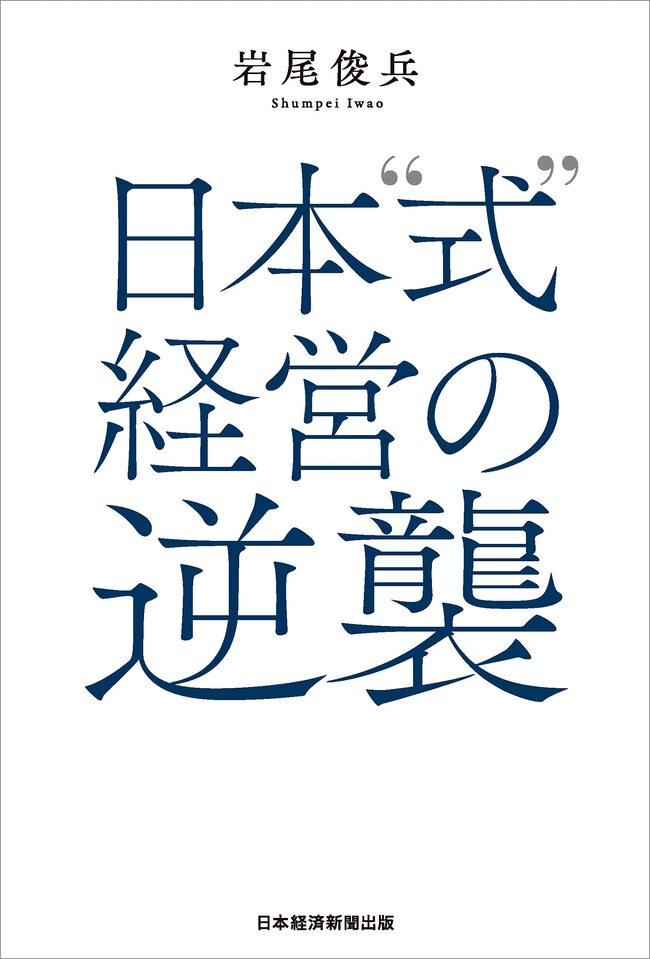「このところの日本企業は、あまりにも自虐的です」と話すのは、慶應義塾大学商学部専任講師の岩尾俊兵さんだ。何の話かといえば「経営学」についてだ。もともと、日本人は「舶来品」に弱い傾向があるが、今や日本の経営学は、海外、特に米国などから“遅れている”という認識が一般的になっているそうだ。
「ところが、外国の経営学の教科書には日本人の名前がたくさん出てきます。それどころか、アマゾンのジェフ・ベゾス氏は、日本の経営から多くを学んでいると公言しています」。
世界的に見れば、日本“式”の経営はいまだに高く評価されているにもかかわらず、日本人自らの評価が”自虐的“と思えるほど低い。「こんな状況はおかしい。日本からも(経営学に関する)新しい情報発信をどんどんして行こう」という気持ちで執筆したのが、『日本”式“経営の逆襲』(日本経済新聞出版)だ。
ここでいう「日本式」というは、「日本型」とは違うことを意図している。「日本型経営」といえば、年功序列、終身雇用などが一般的だが、そうではなく、日本式の経営技術のことだ。経営技術とは少し聞き慣れないが、「経営に関する手法そのものと、その手法を生み出すための実践的な思考フレームワーク」ということになる。ベゾス氏などが注目しているのは、まさにこの日本の経営技術についてだ。
「『両利きの経営』のコンセプトは、日本のカイゼンに関する研究が影響している」
「アジャイル開発、リーン・シンキング、リーン・スタートアップ……。日本の経営実践が源流にありつつもメイド・イン・アメリカのコンセプトとして日本に受け入れられているものは多々ある」
など、本書は、日本が遅れているという感覚と、実態が大きく乖離していることを指摘している。しかも、これによって「残念な結果」まで生じているのだ。
「経営者が英字新聞などを読んで『これはよい経営技術だ。うちでも取り入れよう』などと号令をかけます。しかし、形が違うだけでコンセプトとしては実践済みということが少なくありません。結果として、現場が大混乱に陥るという悲劇につながるのです」
ここまで言うと「やっぱり、日本は凄いんじゃないか! と、逆に自信過剰になる人が出てくることが心配」だと、岩尾さんは話す。極端に振れてしまうというのは、いかにも日本人らしいが、ここは客観的に、少し自分の姿を引き離して見つめ直す必要があるということだろう。
さて、ではどうして日本の経営技術が、日本からではなく、アメリカから発信されるのだろうか?