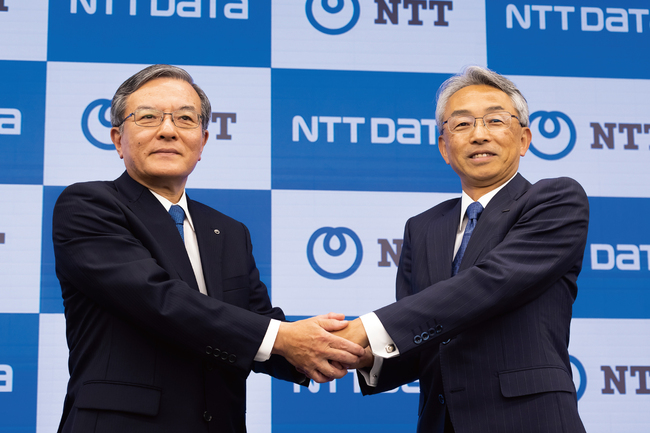今年4月に民営化40年を迎えた日本電信電話が7月から「NTT株式会社」へと社名変更した。さらにNTTデータグループを株式公開買い付け(TOB)により完全子会社化した。ライバルからは「これまでのNTTの分割・民営化の努力は何だったのか」と批判の声も上がるが、NTTにとってグループの再統合は長年の悲願だったようだ。
5月の統合発表会見では昔を知る記者が少なかったせいか、島田明社長に「日本電信電話の名前が消えることに淋しさはないか」と聞くなど本質と関係ない質問に苦笑せざるを得ない場面もあった。というのも、NTTの分割・民営化は通信という公共事業を巡る政治や政府とNTTとの攻防の歴史であり、日本がインターネット時代に立ち遅れる契機を招いた出来事だったからだ。
その分割・民営化されたNTTがなぜ今また再統合しなければならないのか。NTT再統合は日本の情報通信市場における歴史的転換点ともいえるだけに、それが持つ意味を正しく理解する必要がある。それにはまず時計の針を45年前の民営化前夜に戻さなければならない。
「三公社五現業」の見直しから
分割・民営化論がスタート
「三公社五現業」は歴史の教科書に登場する言葉だが、1980年代前半までは鉄道や通信事業、たばこや塩の販売事業は政府直轄の公共企業体が独占的に営んでいた。すなわち日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本専売公社である。いずれも公共企業体ゆえに経営には常に非効率性がつきまとっていた。人事や予算などの経営権は国に握られ、つぶれることがないため、いわゆる「親方日の丸」体質が支配していた。
巨大独占企業である国鉄は80年当時で職員数が約40万人、電電公社も約33万人を数え、どちらも組合活動が盛んだった。国鉄は国家予算の約3割に相当する15兆円もの累積債務を抱えていたが、現場では常にストライキが頻発し、経営はほぼ破綻状態にあった。
電電公社も体質は国鉄と似ていたが、ひとつ違っていたのは通信という事業構造だった。鉄道は列車を毎回運行しなければ収益を得られないが、通信は一度回線を敷設すれば人件費をかけなくても収入が保証された。当時は電話に加入するには「施設設置負担金」や「電信電話債券」を前払いする必要があり、非効率な組織でも収入を得られる仕組みがあったのである。
そんな中で起きたのが80年の電電公社近畿電気通信局不正経理事件、いわゆるカラ出張事件だ。民間企業は経営努力の成果は従業員や株主に還元されるが、公社の場合は国庫に返上しなければならない。それなら経費を架空計上し、裏金を蓄えた方がいいという目論見だった。
そうした組織ぐるみの不祥事が明るみに出たことで電電公社生え抜きの秋草篤二総裁は退任し、代わりに民間から初めて総裁に迎えられたのが石川島播磨重工業(現・IHI)出身の真藤恒氏だ。当時、中曽根康弘首相のもとで行政改革が進んでおり、後に第二次臨時行政調査会(第二臨調)の会長となる土光敏夫氏が推薦したのがIHI後輩の真藤氏だった。