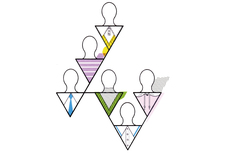Economist誌の7月23日付け公開の社説が、ゼレンスキー大統領が汚職対策の中核をなす反汚職機関の独立性を剥奪する法案を主導したことを、民主化に向けたこれまでの改革の成果を骨抜きにし、対ウクライナ支援の道義的根拠を弱めるものだ、として厳しく批判している。要旨は次の通り(なお、掲載翌日の7月24日に、ゼレンスキーが事実上法案の内容を覆すような新法案を提出したことが、編集者からの最新情報として追記された)。

この戦争におけるウクライナの戦いは、勇気と武器だけでなく、信頼、すなわちウクライナ国民と西側諸国の支持者からの信頼によっても支えられている。この信頼が今、危機に瀕している。
7月22日、ウクライナ議会は、国内の2大汚職対策機関であるNABU(捜査担当)と、SAPO(訴追権限)を大統領府の管理下に置く法案を可決した。これは、ゼレンスキー大統領と、その全権を握るイェルマーク大統領府長官によって上から仕組まれたもので、大統領の党である「国民の奉仕者」党の多数の票を得て可決された。
この法律は、これまでウクライナを支えてきた国際社会の支持を直接脅かすものである。国内では、侵攻以来初めてとなる反ゼレンスキーの抗議運動を引き起こした。
この新法は、大統領によって任命され、大統領に直属するウクライナの検事総長に、汚職捜査にかかる人事異動、捜査への干渉、さらには打ち切りまでも行う広範な権限を与えている。この法律が不当に使われれば、いかなる案件も安心してみていられなくなる。
検察機関に親ロシア派が入り込んでいるという主張は正当化の根拠にはならず、口実に過ぎない。この法律は、10年にわたる民主的改革を後退させ、大統領の統制を再び確立するものである。2014年のマイダン(尊厳)革命以来、ウクライナにとって最も輝かしい国内的成果の一つであった制度的な自律性を骨抜きにするものだ。
Economist誌は長年にわたり、ウクライナの勝利とは、占領された領土からロシア軍を追放することではないと主張してきた。ウクライナの勝利とは、豊かで安定した民主主義国家の出現を意味するのでなければならない。
それは自由主義的価値観に根ざし、法の支配によって統治され、欧州連合(EU)加盟、そして可能であれば北大西洋条約機構(NATO)加盟への道をしっかりと歩む国家である。2つの反汚職機関の設立は、その取り組みの中核を成すものだった。その背後にあるビジョンは、欧米の有権者にウクライナ支援のコスト負担を納得させるのに役立っていたのだ。
しかし、有権者の忍耐力は無限ではない。3年半に及ぶ戦争の終結の兆しが見えない中、西側諸国の多くで、指導者たちは関与の規模の大きさを正当化するのに苦慮している。