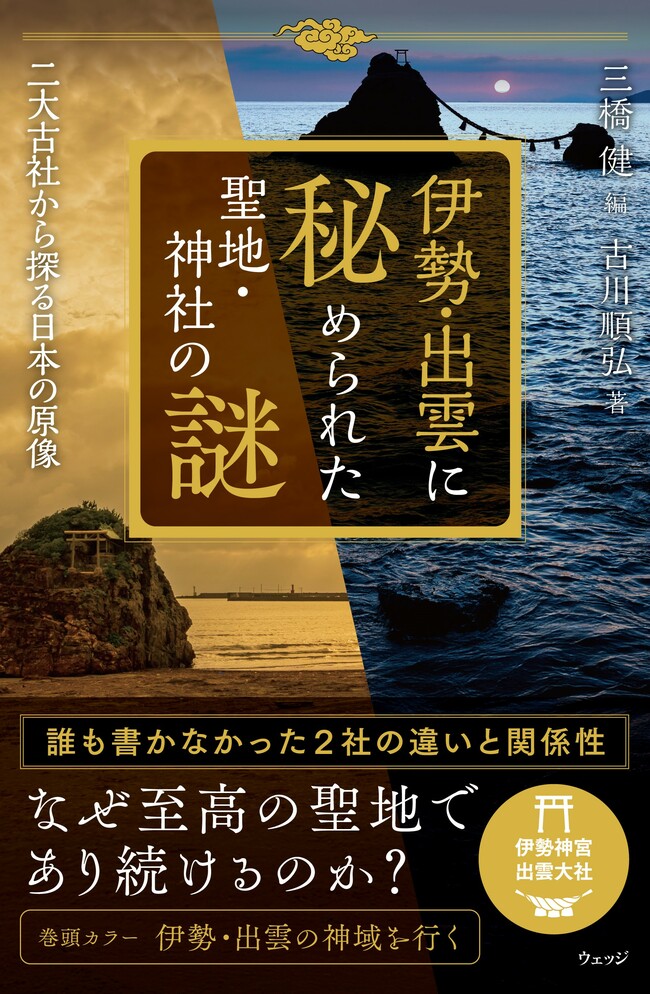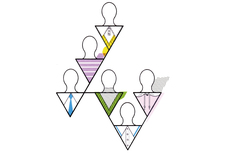しかし、紀元前1世紀の日本は弥生時代にあたり、王朝の存在そのものを想定することが難しい。そもそも垂仁天皇は伝説色が濃い人物で、その実在性に疑念がもたれることもある。そのため、伊勢神宮(内宮)の成立期については諸説が唱えられることになった。代表的なものを挙げてみよう。
①『日本書紀』の記述を信頼し、かつ垂仁朝の年代を3世紀後半~4世紀初頭に比定して、伊勢神宮の起源をこの時期とする(田中卓氏)。
②伊勢神宮はもとは太陽神を祀る伊勢のローカルな神社だったが、大和天皇家の東国への発展に伴い、第21代雄略天皇の時代頃(5世紀後半)から天皇家と関係をもつようになった。これが本格的に皇室の神となったのは古代史上最大の内乱となった壬申の乱(672年)以降のことで、それは、この乱で天武天皇が勝利したのは伊勢の神=天照大神の神助を得たためと信じられたからである(直木孝次郎氏)。
③伊勢神宮が鎮座する度会郡はもとは太陽信仰の聖地で、土着の度会氏が太陽神を祀っていたが、天皇勢力が東方への展開を積極的に進めた雄略朝に、度会に天皇家の神(天照大神)が祀られることになった。これにあわせて従来の度会氏の神は天照大神の食事を司る神(御饌津神/みけつがみ)に変じ、それが外宮の豊受大神(とようけのおおかみ)となった(岡田精司氏)。
②③説は、伊勢神宮の成立を雄略朝(5世紀後半)以降におけるヤマト王権の東方への拡充の産物としている点で共通している。そしてこの立場では、『日本書紀』の倭姫命による天照大神奉遷記事は史実ではなくあくまでも伝承であり、伊勢神宮とそこに仕える巫女の起源を説明するために語られてきた説話だ、という理解になる。
諸説はそれぞれに説得力をもち、悠遠の歴史をもつ神宮の起源を明確にすることは容易ではないが、ここで考古学的な研究をみると、内宮神域からは5世紀代の祭祀遺物が確認されている(穂積裕昌『増補版 伊勢神宮の考古学』)。つまり、考古学上では今のところ、現在の内宮神域で祭祀が行われるようになったのは5世紀からという結論になる。5世紀後半が雄略朝に比定されることを考えれば、このことは②③説に有利にはたらくと言えるだろう。
神鏡とともに殉じた雄略朝の稚足姫皇女
ここで『日本書紀』の雄略天皇の章をひもとくと、伊勢神宮にまつわる伝奇的で美しいひとつの挿話を見出すことができる。
〈雄略朝では、稚足姫皇女(わかたらしひめのひめみこ)が伊勢大神の祠に仕えていたが、あるとき、彼女が廬城部武彦(いおきべのたけひこ)という男と密通して身ごもったという噂がたった。雄略天皇は使者を伊勢に遣わして、皇女を問いただしたが、皇女は知らないと答えるや、にわかに神鏡を持ち出して五十鈴川のほとりに行き、鏡を地中に埋めると自ら縊死(いし)してしまった。
闇夜のなか、行方不明となった皇女の捜索が行われると、川上に虹がかかった。虹が立ったところを掘り返すと、神鏡と皇女の遺骸がみつかった。遺骸の腹を裂くと、液体の中に石があるだけであった。〉(雄略天皇3年4月条)
稚足姫皇女は身ごもっておらず、冤罪をこうむったことが明らかとなるエンディングになっているが、この話自体は、もちろん史実そのままであるとは限らないものの、雄略朝の時点で伊勢の五十鈴川近くの内宮に神鏡(八咫鏡)が祀られていたことを示唆している点で、非常に重要な意義をもっている。五十鈴川の上にかかって闇夜を照らした虹とは、太陽神の御霊代たる八咫鏡から発せられた神異の光だったのか。
付言すると、ヤマト王権の本拠となった奈良盆地南東部からみると、伊勢は日々太陽が昇る方向である東方に位置していた。大和に暮らす人々にとって、伊勢とは、「日の本の聖地」であったのである。