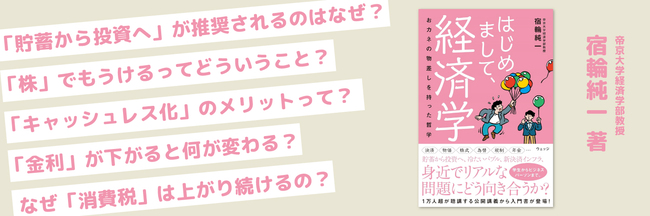加速する「貯蓄から投資」、迎えた「金融政策転換」、景気回復の実態を伴わない「冷たいバブル」…ここ最近、経済に関するニュースが大きな話題を呼んでいます。この身近でありながらも複雑な経済問題について、私たちはどのように向き合えば良いのでしょうか。
今回の記事では、商取引における「情報の非対称性」について解説しています。偽造品の販売、特殊詐欺など、SNSを悪用した詐欺被害が急増しています。商品に対する情報量や交渉力の差を利用して、一般消費者を騙して利益を得ようとする商法は後を絶ちません。
*本記事は帝京大学経済学部教授の宿輪純一氏の著書『はじめまして、経済学 おカネの物差しを持った哲学』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。
今回の記事では、商取引における「情報の非対称性」について解説しています。偽造品の販売、特殊詐欺など、SNSを悪用した詐欺被害が急増しています。商品に対する情報量や交渉力の差を利用して、一般消費者を騙して利益を得ようとする商法は後を絶ちません。
*本記事は帝京大学経済学部教授の宿輪純一氏の著書『はじめまして、経済学 おカネの物差しを持った哲学』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。
社会に蔓延する偽造と隠ぺい
現代社会では、企業によってあらゆるモノが商品化され、私たちはそれを消費して生活しています。そのとき、生産・供給を担っている企業と、一般消費者の間には、商品に関する情報の質と量、そして交渉力に大きな差があります。
これは「情報の非対称性」(Information Asymmetry)とも言われる問題で、企業と一般消費者では、企業の方が格段に多くの情報を持っており、有利な立場であることを示しています。つまり、情報の扱い方によっては、企業は消費者を騙すことも可能であるということです。
ここで中古車市場を例に見ていきましょう。農産物関係者には申し訳ありませんが、中古車市場では古くから粗悪品のことを「レモン」と呼びます。レモンは皮が厚く、外見から中身の見分けがつかないため、このように呼ばれるようになりました。反対に、優良品のことを「ピーチ」といいます。レモンと異なり、ピーチは外見から品質が判断しやすいからです。
中古車市場では、消費者は「できるだけ状態の良い中古車を購入したい」と考えます。しかし、消費者は商品に対する知識(走行距離、事故の有無など)が少なく、限られた情報と見た目の良し悪しから判断せざるを得ません。すべての商品が優良品であれば問題ありませんが、なかには悪徳業者が粗悪品を優良品に見せかけて売りに出しているかもしれません。