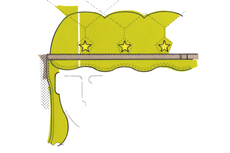生死を分けた11時間の外科手術
私の大腸がん手術は、私の体力を考慮すると、リスクを懸けた戦いであった。ステージ4、すなわち遠隔転移を伴う末期がんである。原発は大腸、転移は肝臓しかも9カ所──主治医は慎重に言葉を選びながら、「11時間に及ぶ大手術になる」と告げた。
手術室の扉が閉じるとき、私はひとつ深呼吸をした。
「これが最後の旅になるかもしれない」
その思いを胸に、静かに目を閉じた。結果的に手術は成功した。大腸の腫瘍を20センチ切除し、肝臓に飛んでいた9カ所の転移巣も同時に切除された。執刀医の卓越した技術と、医療チームの献身的な努力により、私は再びこの世界に戻ることができたのである。
がんの世界で「ステージ4」とは、遠隔転移が確認された最も進行した段階を意味する。国立がん研究センターの統計によれば、大腸がんステージ4の5年相対生存率はおよそ18.7%とされる。数字だけ見れば厳しい現実である。
だが、その中には希望もある。同じステージ4でも、転移巣が手術で「切除できる」かどうかで、予後は大きく異なる。私のように肝転移を切除できた場合、5年生存率は30〜50%に達するという報告もある。つまり、「切除可能」であったという事実こそ、再出発の第一歩である。私はその数字にすがるのではなく、自分の生命力と医療の力を信じてみようと思った。
予想外の試練、うみだまりとの戦い
手術は成功したものの、術後の道のりは平坦ではなかった。肝臓と大腸という2つの大きな臓器を同時に切除したため、体は深刻なダメージを受けていた。最初の難関は「うみだまり」であった。医学的には「膿瘍」や「漿液腫」と呼ばれる状態で、手術部位に体液やリンパ液がたまってしまう。発熱と痛みが続き、私は再び手術台に戻ることになった。
ドレーンを挿入し、体内の膿を外に排出する。局部麻酔とはいえ、痛みは想像を超えていた。だが私は、「これは自然治癒への通過儀礼だ」と心に言い聞かせた。主治医は「場合によっては人工肛門の再造設も考える」と説明した。だが私はその時、きっぱりと答えた。
「先生、時間がかかっても、私は自分の自然治癒力を信じたいのです」と。人工肛門は昔ほど深刻ではなくなりつつあるが、QOLを考えると選択肢に加えたくはなかった。
医療の現場では、科学的根拠(エビデンス)に基づく判断が最優先される。だが、患者にとっては、心の支えや信念も同じくらい大切である。私は、S 主治医に率直に思いを伝えた。
「もし2カ月かかっても、人工肛門ではない自分の体が治る力を試してみたい」
主治医は少し考えた後、静かにうなずいた。
「わかりました。自然治癒力を信じてみましょう。ただし、我々はその力を支える側に回ります」
その言葉を聞いた瞬間、心の底から安堵が広がった。医師と患者が“敵と味方”ではなく、“同じチーム”として歩み出せた瞬間であった。
1カ月の入院、そして再生への道
入院生活は既に1カ月を超えていた。ベッドの上から見える秋の空は、どこか遠く感じた。点滴の針跡、ドレーンの違和感、夜の痛み──それらを乗り越える日々は、まるで修行のようであった。だが私は、焦らなかった。むしろ、「2カ月かかってもいい」と自らに言い聞かせた。
なぜなら、回復は数字で測れるものではないからである。人間の体は、医療だけでなく「心の在り方」にも反応する。私は、体の奥に眠る“治る力”を信じた。看護師の笑顔、家族や孫たちの励まし、友人の手紙──それらが何よりの薬となった。
手術でがんを切除しても、体内にはまだ見えないがん細胞が潜んでいる可能性がある。新たな転移がんの可能性も否定できなかった。そのため、多くの場合は「補助化学療法(抗がん剤治療)」が続く。私も例外ではない。
ゼロックス+バハシズマブ療法という、いわば「第2の戦場」が永遠に待っている。だが私は恐れてはいない。手術という最大の試練を越えた今、どんな副作用が来ようとも受け止める覚悟ができている。何より、私は「命を一度拾った」のである。その時間をどう生きるか──それがこれからの私のテーマである。