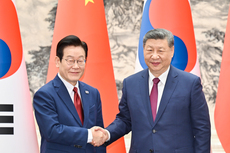憑かれたような南蛮熱
池長の「南蛮狂い」に拍車をかけたのは、妻の正枝が三番目の子を産んだあと産褥熱(さんじょくねつ)で突然亡くなったことだろう。幼子3人を抱えてやもめ暮らしを余儀なくされた池長は、口やかましい母親と同居する兵庫の家を出て、南蛮美術のコレクションという新たな「伴侶」とともに、「紅塵荘」という夢の砦に移り住もうという計画が具体化していった。
スパニッシュ・ミッション様式の「紅塵荘」の新築披露が盛大に行われた。伏見宮博以王夫妻を主賓に迎え、主人の池長は白のタキシード姿で続々と到着する賓客たちを迎えた。やがて、ここで催されるパーティーや舞踏会には南蛮美術の収集を通して親しむようになる作家の谷崎潤一郎や宇野千代、画家の小磯良平や詩人の竹中郁といった神戸ゆかりの文化人たちの顔も見られるようになった。
しかし、残された3人の子たちとともに後添えのような形でこの館の「ご寮はん」となった富子にとって、住み心地はおそらく最初から好ましいものではなかったのだろう。
〈姉はローランサン、池長氏は南蛮絵画、趣味がことごとくちがい、姉のパーティー好き(3階は広大なフロアのパーティー用)、池長氏は教育家でスポーツもゴルフより剣道、姉はゴルフと車。車は二台持っていた。けっきょく別れたが、池長氏はこれはひとときの妻の気まぐれ、再び戻ると決めて巨額のいまなら何十億というべらぼうな別れ金を姉に与え、姉はこれで商売をしようと外国美術品店を思いつく〉
淀川長治は自伝でこのように回想している。

池長孟が南蛮美術の砦を夢見てようやく完成させた「紅塵荘」は、その装飾品として内部を飾る蒐集が十分完成しないうちに新たな女主人に去られて、子供3人を抱えたやもめ暮らしの池長は評価の定まらない美術品の山のなかで、ひたすら蒐集に打ち込んでゆく。その〈南蛮熱〉は「手のつけようもないくらいに狂的になった」と本人がいうほど、歯止めのないものになっていった。
このころ、池長は谷崎潤一郎の知遇を得たこともあって詩や戯曲を手がけるようになった。のちに蒐集品の図録として私家版で出版した『邦彩蛮華大宝鑑』の中で、長崎絵の「阿蘭陀入船図」にそえた「沈める船」と題する詩は、池長の憑かれたような南蛮熱のありかを伝える肉声と言えるかもしれない。
〈沈める船 沈める船
舳を海底に横たへて
折れたる帆柱は砂に埋もれ
艣は巌にくひこんで
天草灘の底深く
永久に沈める南蛮船
羅針盤は何をさすか
海図の皮は水にゆらるるとも
船は動かず
舷側にとりつけられたる
大砲は錆びて朽ちゆく〉