前回はフェイスブックの感情操作実験や研究者の議論から、人の感情とその動員をめぐる可能性とその是非について論じた(http://wedge.ismedia.jp/articles/-/4508)。2014年は感情の動員がひとつのテーマであったとも言えるだろう。無論、2015年を迎えた現在も、ISIL(いわゆる「イスラム国」)によるSNSを通じたネットPR戦略など、人々の感情のフックを利用した動きは常に既に行われている。
しかし、近年にわかに騒がれるようになった問題は、感情を超えて人間存在のあり方そのものが対象になったと筆者は感じている。それこそが、「人工知能」である。今回は近年論じられている人工知能をめぐる問題について紹介したい。
批判も少なくない人工知能
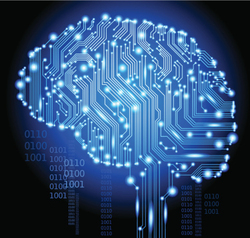 (画像:iStock)
(画像:iStock)
人工知能は20世紀前半から議論が交わされるようになり、1956年に計算機科学者で認知科学者のジョン・マッカーシー(1927-2011)によって命名された。紙面の関係上その歴史について多くを割くことはできないが、その後研究者達が様々なプログラミングを行うことで、推論や学習機能など、様々な要素が人工知能を強化していった。
ただし、技術的な障壁や哲学者からの批判などもあり、研究が行き詰まることもしばしばあった。例えば自分の父親一人をとっても、人間であり、男であり、年齢や職業顔の特徴など、その人を認識するために数多くの認識フレームを人間は無意識で利用している。こうした処理をコンピュータが行うことは(批判当時の技術力では)困難を極めることから、人間同様の知能をコンピュータが持つことは不可能であるとの批判や、また人工知能の振る舞いを細かくプログラミングする必要から、膨大な作業時間を要するとの批判もあった。
人間の「概念」を獲得したディープ・ランニング
大枠でいえば、人工知能研究は80年代に言語処理をはじめとした文法的なルールを中心にした研究が進められていたが、90年代に入ると統計や確率論を用いた研究が注目されるようになる。インターネットが飛躍的な発展をはじめると、グーグルなどの検索サイトは、ユーザーの検索ワードを統計や確率論を用いて解析し、ユーザーの好みのサイトを表示させることに成功した。1から人工知能に教えなくとも、膨大なデータを背景にした確率論によって、人工知能がユーザーの好みを判断するのだ(Amazonのおすすめ機能などがこれに該当する)。

















