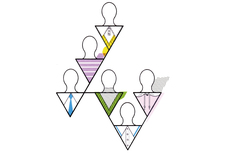冒頭から、心を掴まれた。
「懐かしいような、あるいは全てが夢であったような、もし人生の時間を巻き戻せるなら、あの風景をもう一度だけ見てみたい、というような気持ちだ」
心の中にある〝帰りたい場所〟としてのサーカスという共同体、それを著者は、冒頭で、こんな風に表現する。
「いわば夢と現が混ざり合ったあわいのある場所だった。」
著者の稲泉連さんの母は、作家・久田恵さんである。稲泉さんが3歳の時、期せずして、母子家庭となった久田さんは、その1年後、本橋成一の写真集『サーカスの時間』(河出書房新社)に出会い、本人に連絡をしたことで、キグレサーカスの配膳係として母子で1年半を過ごすことになった。
その大胆な発想と行動力に圧倒されるが、そんなわけで、各地を転々としながらサーカス団とともに暮らした著者が5歳の頃の記憶のかけらが、執筆の源となった。きっかけとなったのは、ある新聞社から、「私の思い出の場所」というお題をいただいたことだという。この時、2011年に倒産したキグレサーカスは、すでにこの世に存在していなかったが、別のサーカス団を訪れたところ、当時の著者をよく覚えていた元キグレサーカスの団員に約40年ぶりの再会を果たすという偶然が著者をその後の取材へと導いた。
こうして著者は、長い歳月を越えて、当時のサーカスという共同体で共に生きた人々に話を聴いて歩くことで、おぼろげな記憶の断片を受肉化していく。
その意味において、サーカスという特殊な場を描きながら、同時に、この本は、万人に共通する捉えがたい記憶というものを巡る物語でもある。
誰にも、輪郭の曖昧な、それでいてさまざまな過去の出来事を差し置いて、心の片隅に居座り続けている記憶の断片というものがあるからだ。
本書の中で引用される詩人、長田弘さんの言葉が、心に刺さった。
〝じぶんの記憶をよく耕すこと。その記憶の庭にそだっていくものが、人生とよばれるものなのだと思う〟