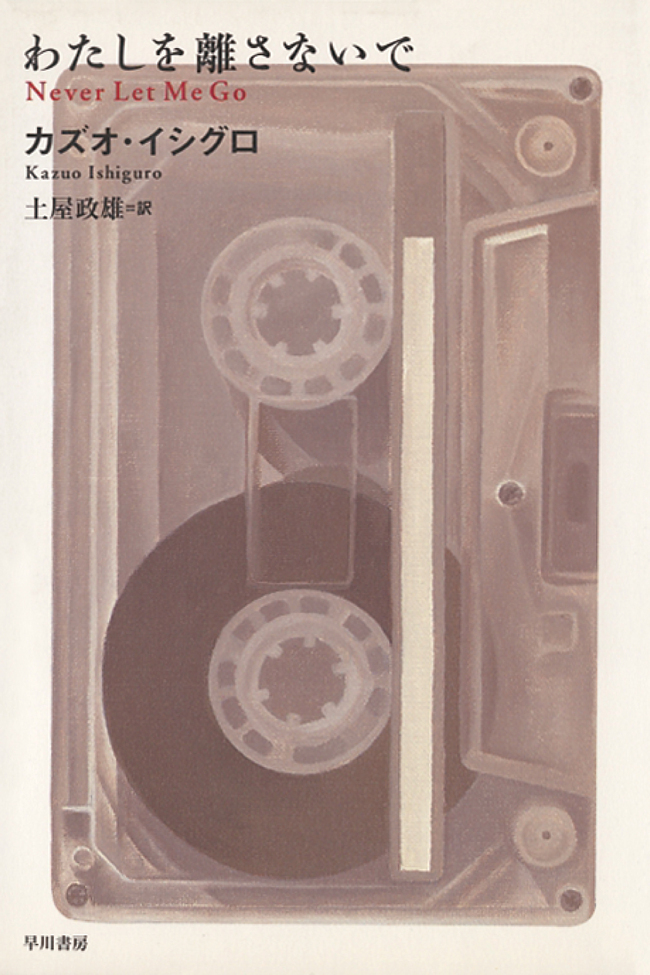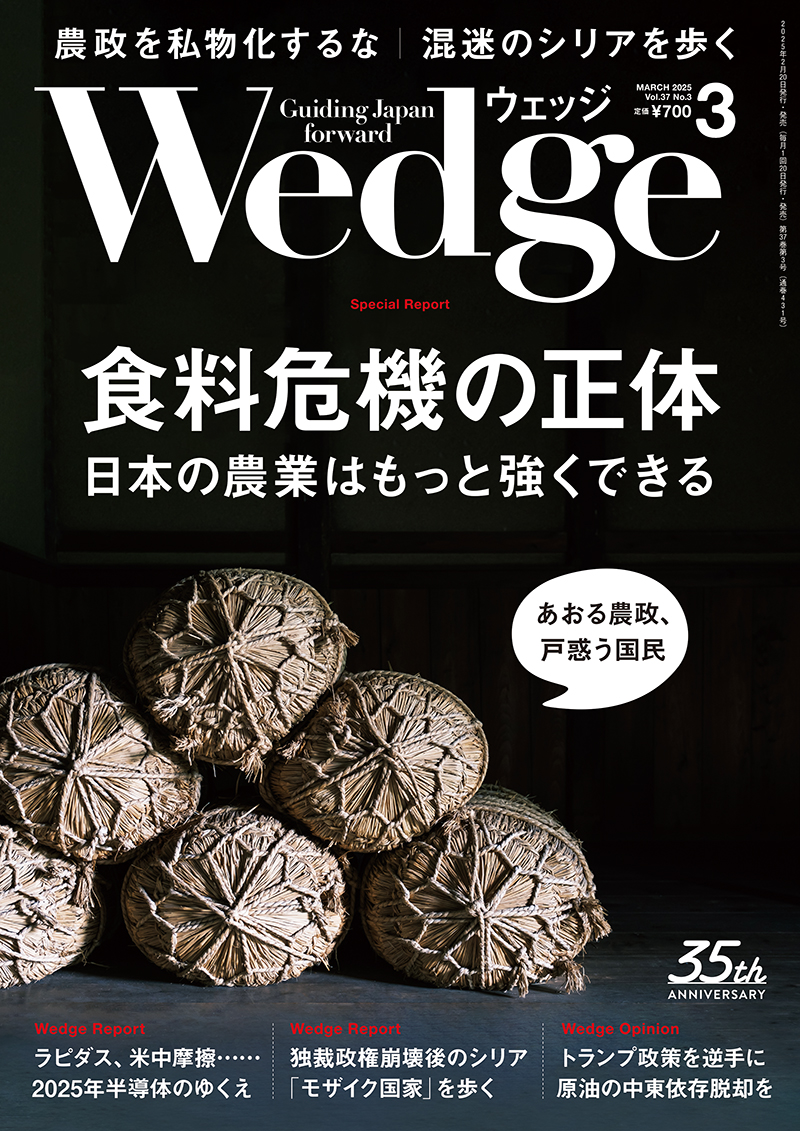瀧口 認識に関する道具に「石ころぼうし」があります。被った人は物理的には存在しているけど、「石ころ」のように誰にも意識されなくなるといったものですが、これも同じように実現できるのでしょうか。
合田 イヤホンなどのノイズキャンセレーション機能と基本的な原理は同じでしょうね。特定のものを「ノイズ」としてキャンセルして書き換えて届けるという。
野村 みんなが脳にチップをつけているような時代になれば、特定の人の存在だけ消すという信号を全員に送ることはできるでしょう。ただ、周囲の人の脳に働きかける必要があるので、「石ころ」になりたい人だけに何かをするだけでは実現できる話ではないですね。
暦本 書き換えでいうと、自動運転によって運転という行動が不要になると、外の景色はVRにして全部書き換えるという話もありますよね。道路でトラックに追い越される代わりに、サバンナでキリンに追い越されたように見えるという。
加藤 物理的には実現ができないことでも、テクノロジーによって疑似体験はできるものもあるということですね。
野村 そういうものは多いでしょうね。「どこでもドア」も今の量子テレポーテーション技術では難しいかもしれませんけど、「Zoom」などを発展させる形で、事実上、同じ機能を実現できるかもしれないですから。
暦本 『ドラえもん』はそういう発想訓練にもなりますよね。真正面は難しいけど、こういう迂回をすれば同等のことはできるんじゃないか、みたいな。
SFが
世界を救う?
瀧口 こうやってSFのアイデアを考えているとビジネスにつながることもたくさんありそうですね。
暦本 イーロン・マスクのような人たちはSFの世界を実現したくて仕事をやっているんじゃないでしょうか。子どもの頃からたくさんのSFを読んでいて、火星に住むのも突飛な話ではなくて、到達できる現実的未来だと思っているような気がします。SF発の事業やビジネスという面では、ビジネスパーソンや起業家にSFファンが多いアメリカはやっぱり強いですよね。
瀧口 SFは国力を表すといわれることもあります。最近実写ドラマ化され話題になった、中国人SF作家劉慈欣による長編小説『三体』なんかも、勢いのある国だからこそ生まれた作品かもしれませんね。
合田 実験科学者という身で研究をやっていると物事を「実現させること」を基準に考える癖があるんですよね。でも、実現性ばかりを突き詰めていても、結局いいアイデアは生まれません。だからこそ、SFみたいな〝ありえない世界〟を見ることは研究においても重要なんです。
野村 日本ではアメリカほどSFはメジャーではないので、SF好きってちょっと〝オタク〟扱いされてしまうかもしれません。でも、国力を上げるためには、「オタクの方がモテる」くらいに、興味のある分野を恥ずかしく思ったり、隠さないで済むようにならなければ駄目だと思いますね。
加藤 日本の若者世代では「オタク文化」はすでにある程度築かれていますからね。SFオタクがどんどん地位を確立していってほしいですね。
暦本 SFって技術力の向上の話だけでなく「文学」としても重要な役割があって、社会の変化や問題を「SF」として作品に落とし込むことで社会課題になりうることを先行して考えることができるんです。
例えば、2017年にノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの小説『わたしを離さないで』は臓器提供するためにクローン人間が作られた世界の話ですが、クローン人間は臓器提供を終えると死んでしまう。現実でもクローン技術というのは着実に進歩していて、でもクローン人間に関する倫理観というものを真正面から議論するのは非常に難しい。だからこそ、「SF」作品とすることで、文学でしか議論できない領域と向き合うことも現代にとっては重要なことだと思います。
SFはそれ自体がとても面白いのはもちろんですが、日本を救う、世界を救うといったことにおいても非常に重要な存在であると思っています。皆さん、もっとSFを読みましょう。