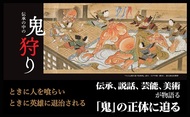最新記事一覧
「BBC News」の記事一覧はこちら-
2026/02/17 斎藤 彰
「大国に迎合しても安全は買えない」――。米国のトランプ大統領の常軌を逸する強権発動や脅しに国際社会がひるむ中、隣国の指導者として敢然と立ち向かうカナダのマーク・カーニー首相の言動に内外で大きな反響と賛辞が寄せられている。
-
2026/02/17 中村繁夫
ステージ4は「一度の手術」では終わらなかった。ステージ4という診断は、単なる医学用語ではない。それは私の人生に突きつけられた「長期戦」の戦況報告であった。私の闘いは、一度の大手術で終わらなかった。実態は、4回の手術を連続してくぐり抜ける長…
-
2026/02/17 岡崎研究所
ベネズエラでの作戦に成功したトランプやルビオ国務長官は、次はキューバだと意気込み、何らかの交渉が行われていることを示唆している。キューバへの石油輸出を続けるメキシコがトランプ政権と衝突し、経済関係に悪影響が及ぶことを懸念される。
-
2026/02/16 田中淳夫
世界中で木造ビルの建設がブームとなっている。環境負荷の低さや林業の活性化を図ってのことのようだが、現実を直視すると「木造ビルの不都合な真実」が見えてきた……。
-
2026/02/16 佐藤俊介
ロシアがウクライナの民間施設への攻撃を激化している。マイナス20度を下回る極寒での住民生活を守る電力施設や発電所への攻撃に加え、鉄道や民間バスまでも標的にしている。依然としてその決着をつけられないプーチン大統領の焦りがある。
-
2026/02/16 中川コージ
人口はすでに世界一、国内総生産(GDP)も日独を抜いて第3位となるのも秒読みのインド。中国との接近が目立つが、事態は単純ではない。米中印G3世界では、複雑な戦略が求められる。
-
2026/02/16 岡崎研究所
トランプ関税が発表された頃の東南アジアの先行きは暗いものだったが、この悲観論を裏切り、目覚ましい底力を示している。昨年の対米輸出は増え続け、主要工業国への海外直接投資も、供給網の多角化を背景に増加している。
-
2026/02/15 吉永ケンジ
韓国の安圭伯国防部長官が訪日し、小泉進次郎防衛大臣の地元・横須賀市で会談し、9年ぶりとなる日韓海上捜索救助訓練の再開に合意した。一方、カナダ国防調達担当大臣が韓国の潜水艦を視察した。次期潜水艦事業に韓国防衛産業の未来を託している。
-
『雨に祟られた晩秋の南北ベトナム、中国国境の町からサイゴンへ』 第2回
2026/02/15 高野凌11月21日。ベトナム北部の観光拠点カオバンのホステルのオーナー兼マネージャーのアラフォーの女性と歓談。ホステルは5階建てで古びているが、室内やリネン類が清潔で繁盛している。小学生の息子を英語塾に通わせており、将来は待遇の良い外資系企業に…
-
豊臣兄弟のマネー術第1回
2026/02/15 橋場日月始まりましたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』。秀吉(藤吉郎)が信長に仕え、弟の秀長(小一郎)がそれについていった。秀吉が最初にもらった所領はどれほどで、秀長がドラマの初回に参加した清須の道普請の賃金はどれほどだったのか。
-
2026/02/14 ウェッジ クロスコンテンツ室
近年、映画やアニメで人気を集める「鬼」や妖怪。しかしそれらのルーツは、遥かなる日本の歴史と民俗に深く根差しています。それは、現代人が忘れかけた「日本人の心の闇と光」そのものなのです。
-
日本不在のアジア最前線─教育と低リテラシーが招く空洞化 第4回
2026/02/14 桂木麻也本稿では、教育を「国家の実装能力」という観点から捉え直し、立ちすくむ日本を動かすための再設計を考えていきたい。
-
2026/02/14 石村博子
「シベリア抑留」というと軍人の悲劇という印象が強くあるが、その中には市井の人々もいた。「シベリア民間人抑留者」は異国の地で、自らの運命を受け入れ、格闘し続けた人々であった。
-
2026/02/13 冷泉彰彦
トランプ大統領が次期FRB議長にケビン・ウォーシュ元FRB理事を指名したことを受けて金が一時的に暴落した。この人事と指名直後の「ショック」には複雑な背景がある。日米関係の今後も含め当面の考察をしてみたい。
-
2026/02/13 長尾 賢
トランプ大統領とモディ首相は、アメリカとインドの貿易合意が締結されたことをSNS上で発表した。両国は感情的な対立があったのに、どのようにして突破口が開かれたのだろうか。背景をみると、インドの交渉における強みが反映されたことが考えられる。
-
2026/02/13 片野 歩
シシャモが大漁です。日本ではなく、アイスランドのカラフトシシャモです。日本がほとんど水揚げされなくなっている中、アイスランドやノルウェーでは漁獲量が多く、魚価も日本が30倍以上となっています。なぜなのか?
-
2026/02/13 岡崎研究所
イランのイスラム革命体制は、強硬な弾圧で反政府デモを乗り切ったように見えるが、革命防衛隊のクーデーターの可能性も排除されない。命体制が崩壊すれば、かえってイランが混乱する可能性もあり、引き続き危険な不確実性をはらんでいる。
-
2026/02/12 廣部 泉
年に一度の音楽の祭典グラミー賞に対し、トランプ大統領が「最悪で見られたものじゃない」と嚙みついた。司会者を訴えることまで示唆している。何がそんなにトランプを怒らせたのか。
-
2026/02/12 渡邊啓貴
高市早苗首相の突然とも言える解散表明による衆議院総選挙は、自民党が3分の2の議席を獲得する「歴史的勝利」で幕を閉じた。解散表明をした会見で、「国民に新政府に対する信任を問う」と語った高市首相の〝思い〟はかなったのか?
-
2026/02/12 岡崎研究所
中国の工作員による台湾軍に対するスパイ活動が急増している。近年、中国による台湾への諜報活動が活発化しているが、中国による台湾への軍事侵攻の準備に関連していると思われる活動は、これに止まらない。
|
|
|