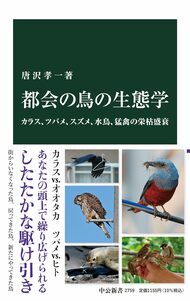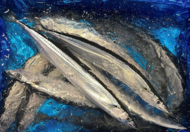-

キーワードから考える財政問題②
2023/09/24 島澤 諭税の好調な自然増収を受けて、内閣府はプライマリーバランスの黒字化が目標の26年度に達成される見込みと試算している。ただ、これに関しては、歳出・歳入の構造改革によるか、経済成長による税の自然増収によるかの路線対立があり、見極める必要がある。
-
 2023/09/24 関谷次博
2023/09/24 関谷次博「2024年問題」は、近年始まった問題ではない。1960年代から、人手不足はトラック輸送に宿命のようにつきまとっていた。
-

鯛ちりめん
2023/09/24 水代優季節を楽しむために訪れるお店があります。京都・四条河原町の交差点から「真橋通り」という小さな路地に入ると、「加茂川の西 河原町の東 汁」と描かれた暖簾が見えてきます。今回のお土産は「鯛ちりめん」です。
-

都会の鳥の生態学 カラス、スズメ、水鳥、猛禽の栄枯盛衰』唐沢孝一氏インタビュー
2023/09/23 足立倫行ツバメ、スズメ、カラス、ヒヨドリ、キジバトなど、都会に生息する身近な野鳥は「都市鳥」と呼ばれる。『都会の鳥の生態学 カラス、スズメ、水鳥、猛禽の栄枯盛衰』(唐沢孝一、中公新書)。彼ら都市鳥と人間との関係は時代と共に変わってきた。換言すれば…
-

静岡県御殿場市
2023/09/23 羽鳥好之東京からもアクセスのよい東名高速の御殿場インターからほど近く。首相を務めた岸信介が晩年の17年間をすごした、こだわりの自邸がある。
-
 2023/09/23 保手濱彰人
2023/09/23 保手濱彰人人の意識は時代の変遷とともに成熟していく、という「インテグラル理論」の概説を本連載では何度か説いた。暴力と支配のレッド段階を表す『北斗の拳』(武論尊、原哲夫、集英社)、ルールと規律のブルー段階の『島耕作』(弘兼憲史、講談社)に続き、平成以…
-
 2023/09/22 鬼頭宏
2023/09/22 鬼頭宏急加速する少子化に、どうすれば子どもが増えるかが日々議論されている。そもそも人口が減ることは悪いことなのか─。今の議論に足りない視点を説く。
-
 2023/09/21 福地亜希
2023/09/21 福地亜希経済統合を着実に進めてきたASEANの中で特に進展が見られるのが、金融リテール分野だ。このダイナミズムは日本企業にとってもチャンスとなる。
-
 2023/09/20 片野 歩
2023/09/20 片野 歩かつて毎年8月末頃から1尾100円前後で売り場を埋め尽くしていた秋の風物詩サンマ。しかし、その光景はすでにありません。「今年こそは」と期待しても、すでに諦めている方は少なくないはずです。なぜなら、日本の漁業そのものに問題があるからです。
-
 2023/09/20 石井順也
2023/09/20 石井順也混沌とした情勢や米中対立の激化に、「したたかな現実主義」で対応するASEAN各国。インド太平洋戦略における中核的パートナーに対し、日本はどのように臨むべきか。
-

エネルギー基礎知識②
2023/09/18 山本隆三エネルギーには多くの種類があり、埋蔵量に限りがある石油、石炭から、使ってもなくならない再エネまであります。ですが、100点満点のエネルギーはありません。どのようなエネルギーを使えばよいのでしょうか。
-

少子化に向き合う海外諸国 現地の専門家に聞く
2023/09/18 高崎順子人口減少社会は日本だけでなく、諸外国にとっても喫緊の課題だ。フランスと中国の〝現在地〟を垣間見ながら、日本への示唆を読み解こう。
-
 2023/09/17 吉永ケンジ
2023/09/17 吉永ケンジ四半世紀以上にわたり自衛隊で人的情報活動に携わってきた筆者は、TBS曜劇場「VIVANT」で自衛隊秘密組織といわれる「別班」がヒーロー視されていることに、戸惑いを隠せない。秘密のベールに包まれた自衛隊のインテリジェンスの真の姿を紹介してい…
-
 2023/09/17 大城慶吾,野川隆輝
2023/09/17 大城慶吾,野川隆輝時間外労働の上限規制への対応(2024年問題)、深刻な高齢化、なり手の不足……。持続可能な建設業にするには何が必要なのか。日本建設業連合会の宮本洋一会長に聞いた。
-
 2023/09/16 佐々義子
2023/09/16 佐々義子「あなたの最後の晩餐はなんですか」。時に聞かれる問だが、現実は健康を害すると食事が制限され、好きなものを我慢しなくてはならないことがある。ここに、チョコレートで嚥下障害の高齢者や難病患者の食生活の質を上げようと挑戦している医師がいる。
-
 2023/09/16 勝股秀通
2023/09/16 勝股秀通防衛力の抜本的強化のためには「ヒト」に関する議論が欠かせない。自衛隊が本来の任務を全うできなくなる前に、真剣に向き合うべきだ。
-

どちらが優先?花粉症対策と森林保全②
2023/09/15 中岡 茂林野庁の概算要求を見ると、「花粉症対策」で「国産材の供給・利用量の増加」「木材輸出の強化」「担い手の育成・確保」と、実現性の低いものが並ぶ。細々ながらも継続されていた木材生産としての林業は、花粉症対策によって壊滅することになるだろう。
-
 2023/09/14 岡田 豊
2023/09/14 岡田 豊大手百貨店の西武池袋本店で、大手百貨店では約60年ぶりのストライキが行われた。労働者が声をあげることへ賛同の声も出ているが、西武百貨店の路線転換は起こるべくして起きたことといえる。変革しなければ、根本的解決にはならない。
-
 2023/09/12 原田 泰
2023/09/12 原田 泰エネルギー価格の高騰に対して、日本ではエネルギー関連の補助金で乗り切ろうとしている。この補助金は2023年9月末までで6兆円、12月まででさらに1.2兆円かかるようである。安易に補助金を支給し続けていて良いのだろうか。
-
 2023/09/12 多賀一晃
2023/09/12 多賀一晃日本の賃金の低さがメディアを賑わしている。一方、海外で生産していたルームエアコンが、再び日本で生産を始めている。明確に語られないが、生産コストを追求して海外生産するメリットより、市場ニーズを、間を空けず満たすことができるリードタイムの短さ…
|
|
|