お花畑の農業論にモノ申す
中国による食料・農地の囲い込みや新型コロナウイルスによるサプライチェーン変革、スマート農業をはじめとする先端技術の活用など、世界の食料事情は変革が起き続けている中、「田園回帰」や「農家の保護」といった夢物語の農業論ではなく、輸出入や農地の集約と役割分担、農業経営改革といった予算ありきでない農業政策が求められる。
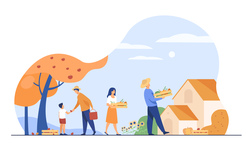
-
 2023/05/29 渡辺好明
2023/05/29 渡辺好明「食料危機に備え法制度」という報道を見て、なぜかデジャビュに襲われた。「まさかこの時代に」と思うのだが、食料・農業・農村基本法見直しを検討している農水省の審議会の『中間とりまとめ案』にも、盛り込まれている。コメントを加えたくなった。
-
 2023/05/12 福田浩一
2023/05/12 福田浩一マスコミではその存在意義を疑われることが多い農協だが、生産者にとって一番身近な組織であり、食の安全などを含めた高品質な農産物を維持しながら生産者を支えてきたのは間違いない。批判だけでなく、利点を冷静に見ることも必要なのではないか。
-
 2023/05/03 渡辺好明
2023/05/03 渡辺好明大阪の堂島取引所によるコメ先物取引の「本上場の申請」に対して、農水省は自民党との議論を経て「不認可」としたが、やはり現物と先渡、先物が分担・連携・総合化していくことが理想である。歴史的な正当性や世界の常識との乖離を解説したい。
-
 2023/05/02 渡辺好明
2023/05/02 渡辺好明「コメ現物市場」の姿かたちが見えてきた。コメ業界に70年以上存在しなかった公的な「自由な流通・取引の場」が生まれる。生産、流通、消費にいかなる効果が生じ、健全な発展につながるのか。歴史的経緯も含めておさらいしてみたい。
-
 2023/04/13 福田浩一
2023/04/13 福田浩一三重県では多くの先進的な生産者に会うことができた。こうした生産者らは、かつての「農家さん」のイメージからかけ離れており、中小企業などの経営者に近い。実は、他県でもこのような農業経営者に会うことは多く、この傾向は全国的なようだ。
-
 2023/03/24 福田浩一
2023/03/24 福田浩一2023年年明け早々、シンガポールを訪問し、日本企業の飲食店が活況を呈し、日本産農産物が現地消費者に人気であるのを目の当たりにした。農林水産物・食品の輸出額を25年に2兆円、30年に5兆円を掲げる日本にとって重要な課題が見て取れた。
-
 2023/02/13 渡辺好明
2023/02/13 渡辺好明昨年末に取りまとめられた「食料安全保障強化政策大綱」を、「鳥の目、虫の目、トンボの目」と、見る角度を変えながら注目点を読み解く。その意図するところ、実現への道筋、留意点、乗り越えるべき障害などについて見ていく。
-
 2023/01/13 熊野孝文
2023/01/13 熊野孝文たんぱく質を特殊な加工法で除去した日本発の「低たんぱく加工玄米」が新たな付加価値を持つコメとして、国内外から注目されている。コメの持つ価値を科学的に解明し、生産から商品化まで手掛け、国内外に広める新たな取り組みが動き出している形だ。
-
 2022/11/04 山口亮子
2022/11/04 山口亮子家畜の細胞を培養して作り出される「培養肉」。その開発に各国がしのぎを削るなか、日本の開発現場はどんな強みを持ち、どんな課題にぶつかっているのか。「培養フォアグラ」を世界で初めて生産したスタートアップのインテグリカルチャーを取材した。
-
 2022/11/02 熊野孝文
2022/11/02 熊野孝文米穀専門小売店はコメの流通規制が撤廃されてから急激に数を減らしている。米穀小売店はそれぞれ独自の路線を模索し、存続しようとしている。また、コメの大切さや美味しさを伝える地道な活動も展開し、お米ファンを増やすことにも寄与しようとしている。
-
 2022/10/10 渡辺好明
2022/10/10 渡辺好明ウクライナ戦争による食料サプライチェーンの崩壊で、日本国内でも飼料価格の高騰が叫ばれている。この対策として、畜産用「子実用トウモロコシ」の生産振興が図られようとしているが、事を急いではいけない。
-
 2022/10/03 熊野孝文
2022/10/03 熊野孝文コメの需要は毎年減り続けているとされ、その需給を均衡させて、価格を維持するために主食用米の生産を減らそうと巨額の税金が投入され続けられている。しかし、農水省が言うコメの需要とは一般人の感覚からすると首をかしげてしまう事例が多い。
-
 2022/09/20 渡辺好明
2022/09/20 渡辺好明政府の「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」は、「食料・農業・農村基本法」の見直しを決めた。この際、正しい理解と共通認識があるようで無い「食料自給率」について、各都道府県と諸外国・地域の数字を比較し、今後の日本の歩む道を明らかにする。
-
 2022/09/10 熊野孝文
2022/09/10 熊野孝文消費者のコメの選択肢を増やすはずの農産物検査法改正が二律背反の結果を招いている。コメ管理のデジタル化で多様な価値を世界へも伝えようとしてい るが、新たな書類の提出などさまざまなデータを検査して入力しなければならない結果を招いている。
-
 2022/08/11 山口亮子
2022/08/11 山口亮子品種の育成者に知的財産権を認め、その権利を保護する改正種苗法が今年4月、ひっそりと完全施行された。一時〝農家を苦しめる改悪〟だとして反対運動が盛り上がっていたものだ。その喧騒が過ぎ去り、今起きていることとは。
-
 2022/08/04 熊野孝文
2022/08/04 熊野孝文コロナ禍やウクライナ紛争による世界的な穀物相場高騰により、日本米輸出に追い風が吹いている。しかし、日本のコメ産業には制度上、第三者には理解しがたい足かせがはめられており、輸出業者の自由な商活動に支障を来す問題が横たわっている。
-
 2022/07/23 田牧一郎
2022/07/23 田牧一郎米国カリフォルニア州のコメの作付面積と生産量が3年続いた干ばつにより大幅に減少していることがわかった。価格の高騰のみではなく、将来への供給不安はヨーロッパはじめ輸出マーケットにも広がる。日本のコメ産業にとって大きなチャンスとなり得る。
-
 2022/06/29 熊野孝文
2022/06/29 熊野孝文新潟県十日町の星峠棚田に行ってみた。2019年に議員立法で成立した「棚田地域振興法」により進められている支援策の実態を見るためであったが、見聞きしたことは日本の稲作が置かれている厳しい現実であった。
-
 2022/06/14 渡辺好明
2022/06/14 渡辺好明穀物の大輸出国ウクライナでは、戦火により積み出しが不可能となっている。「物流」の途絶・中断が生じている背景には、ウクライナの海外輸出が「黒海沿岸の3地域」に集中していることにあるのではないだろうか。考えられる対応策を列記してみたい。
-
 2022/06/07 渡辺好明
2022/06/07 渡辺好明食料危機が、現実感を帯びてきた。食料の需給ひっ迫状態は今後も続くだろう。日本でも注目が高まりつつある食料危機対応策を万全にするために4つの視点をぜひ加えたい。
|
|
|

























