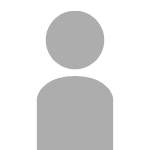-
 2024/12/19 岡崎研究所
2024/12/19 岡崎研究所台湾の中では現実論として、台湾防衛にとっての米国の重要性がより多くの人々に受け入れられつつある。トランプ第2期政権の顔ぶれを台湾はプラスにとらえているが、トランプ氏の台湾に対する様々な発言に不安も残る。
-
 2024/12/18 岡崎研究所
2024/12/18 岡崎研究所印中国境問題を見れば、トランプ政権下での米印関係の行方はそれほど悪くない。インドにとって最大の戦略的脅威は中国であり、トランプと利を一致する部分も多い。それは、日本とも似た状況であると言える。
-
 2024/12/17 岡崎研究所
2024/12/17 岡崎研究所米国がウクライナに供与した長射程兵器のロシア領内への使用を認めたことに、ロシアの核使用へエスカレーションが注目された。プーチンにとって、核兵器による攻撃は、論理的に想定されるものの、得るものが少なく、失うものが甚大と考えたとみられる。
-
 2024/12/16 岡崎研究所
2024/12/16 岡崎研究所米中貿易戦争以降、一番恩恵を受けてきた国の一つがベトナムだ。貿易黒字は近年、世界4位。ただ、輸出の3割近くを米国に依存しており、トランプ政権発足に備え、巨額の貿易黒字に関するリスク分析と対応策策定に努めているのは間違いない。
-
 2024/12/13 岡崎研究所
2024/12/13 岡崎研究所イランは自国へのイスラエルの報復を避けるために、イラクを利用するとみられる。すでに新たな代理勢力を構築しており、イラクが次の衝突の焦点となるかも知れない。ただ、イスラエルからの報復は避けられず、尻込みする部分も出ている。
-
 2024/12/12 岡崎研究所
2024/12/12 岡崎研究所2期目のトランプ政権は1期目とは異なった世界に直面し、姿を消した相手もいれば強大となった者もいる。トランプの視座(「ドクトリン」)ではなく、米国を取り巻く外的環境(「出来事」)によって、トランプの外交が規定される。
-
 2024/12/11 岡崎研究所
2024/12/11 岡崎研究所タイとマレーシアに続き、インドネシアが、昨年一旦拒否したBRICS加盟を表明した。これらの申請は、2つの意味で注意を要する。これらを踏まえ、日本として早急にやるべきことが出てきている。
-
 2024/12/10 岡崎研究所
2024/12/10 岡崎研究所トランプと共和党の圧勝の意義は、米国の有権者がリベラリズムや1980年代以降の「自由社会」の理解を決定的に否定したことにある。フランシス・フクヤマは、今回のトランプ圧勝の背景と今後の見通しについて、極めて納得できる説明をしている。
-
 2024/12/09 岡崎研究所
2024/12/09 岡崎研究所中国の一帯一路は、流入資金が減少しているが、使命を終えているわけではない。大規模なインフラ投資から通信、AIなどのより付加価値の高い新フロンティア部門優先に「進化」しつつあり、付加価値の高いデジタル経済への移行につながる効果もある。
-
 2024/12/06 岡崎研究所
2024/12/06 岡崎研究所前政権時に歴代米大統領の中でも極端に親イスラエル姿勢を示したトランプ次期米大統領の中東政策に関心が集まっているが、それは誰が彼に中東政策を吹き込むかによるだろう。注目は、トランプ氏の気まぐれさと武力行使を嫌う性格がどう影響するかだ。
-
 2024/12/05 岡崎研究所
2024/12/05 岡崎研究所過激で予測不能のトランプへの権力移行という大きな変動の過程に当たる中、この間隙を突いてロシアがイスラエル、中国が利得を得るべく狡猾な行動に出る可能性がある。
-
 2024/12/04 岡崎研究所
2024/12/04 岡崎研究所中国が長期戦略に基づき北極への関与を進めている。関与にはロシアとの協力が不可欠であり、ウクライナ侵攻以降、協力が急速に進展しており、米国が脅威と感じている。
-
 2024/12/03 岡崎研究所
2024/12/03 岡崎研究所「戦争は、始めるのは易しいが終らせるのは難しい」と言われるが、プーチンは今かなり困っていると判断していい。ウクライナでの公正な平和のチャンスを最大化するために西側の支援者はその力を示す必要がある。
-
 2024/12/02 岡崎研究所
2024/12/02 岡崎研究所トランプ政権となれば、米中貿易戦争は不可避となる。中国の経済停滞や債務増大がこの交渉に脆弱との見方もあるが、トランプの無知、焦点の欠如、縁故主義、騙されやすさの4つの特性がこの問題への対応として最悪であるとの見方もある。
-
 2024/11/29 岡崎研究所
2024/11/29 岡崎研究所イランは核保有の一歩手前で開発を止めているとみられているが、イスラエルとの対立が直接的な攻撃の応酬の段階に至り、核保有に向かうという予測を耳にする。ただ、国際関係は「力」の原理だけで動いているわけではない。
-
 2024/11/28 岡崎研究所
2024/11/28 岡崎研究所ゼレンスキーが、バイデン政権の支援に苛立ちを強め、ワイルドカードのトランプに賭けてみる気になったようだ。ウクライナの当局者は公になっている二つの案を基に検討している。ただ、そこにはプーチンの出方という問題もある。
-
 2024/11/27 岡崎研究所
2024/11/27 岡崎研究所インドネシアとロシアが初の海軍合同訓練を開始した。米、中、露の間でバランスを取ろうとしているようだ。米国は紛争解決への意思をほぼ失っており、日本を含む米国の同盟国・同志国が紛争解決実現という「挑戦」をシェアする必要がある。
-
 2024/11/26 岡崎研究所
2024/11/26 岡崎研究所トランプが世界を見る時、基本的な視座は安全保障の観点からではなく、経済・ビジネスの観点からである。日本は、そうしたトランプの世界観に乗っかった上で議論する必要がある。
-
 2024/11/25 岡崎研究所
2024/11/25 岡崎研究所イーロン・マスクが大統領選挙4カ月前にトランプ支持を明確にし、支援の見返りに何を求めるのか注目されていた。マスクとトランプは2つの重要な問題で考え方が異なり、留意すべき点を整理してみたい。
-
 2024/11/22 岡崎研究所
2024/11/22 岡崎研究所BRICSは、予想以上の速さで加盟国を拡大し国際社会における「発言力」は増え、既存の秩序への抵抗勢力としても一層正統性を高めていくのは不可避だ。それに対して、既存勢力である西側諸国は何をすべきなのだろうか。
|
|
|