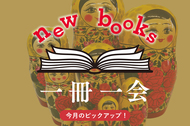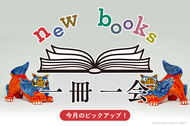「社会」の最新記事一覧
-
 2025/07/21 Wedge ONLINE編集部
2025/07/21 Wedge ONLINE編集部全国各地でクマの目撃や被害に関する情報が出ている。もはや、クマの出没や被害は「異常現象」ではなくなりつつある。現代社会において、日本人がクマとどう生きていくのか。検証した記事を紹介する。
-

-

第3回 麻布山善福寺「逆さイチョウ」(東京・港区)
2025/07/19 堀川晃菜大都会に深く根差すその木は、この世の希望も絶望も、全て包含しているかのようだった──。推定樹齢750年の巨木は80年前「戦災樹木」となった。折しも日米関係の礎が築かれた寺で、木は何を見たのか。時代の番人として生き続ける「逆さイチョウ」を紹…
-
 2025/07/18 田中淳夫
2025/07/18 田中淳夫琉球王朝の象徴とも言える首里城の復元現場が進められ来秋終了予定だ。歴史的建造物の復元は各地で行われているが、それらの計画・構想には様々な意見が交錯する。メリット・デメリットを考えてみたい。
-
 2025/07/17 井原 裕
2025/07/17 井原 裕参議院選挙の投開票を控え、SNS上ではすでに熱気を帯びた言論戦が展開されている。この言論の舞台が、理性的な市民社会の基盤を広げているのか、それとも、「衆愚の広場」と化しているのか、問い直すべき時期に来ている。
-
 2025/07/17 川﨑真規
2025/07/17 川﨑真規TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』で松本潤さん演じる徳重晃のような特定の病気に限定せず患者という「人」全体を包括的に診る医師がいて欲しいと思う視聴者も多いだろう。実は、徳重のような医師は日本にも存在する。では、なぜ、出会うことが少ないの…
-
 2025/07/16 吉田浩
2025/07/16 吉田浩沖縄社会の発展と改善は日本にとって重要な政策的課題であるとされている。戦後80年を経るうちに沖縄県はどう変化したのか。社会を人口構造の面から見ていく。
-
 2025/07/16 唐木英明
2025/07/16 唐木英明参院選の各政党の政策を見ると、一部の政党が消費者の食への不安を政治的に利用し、科学的に根拠のない政策を提案している。これらの政策は、科学に対する国民の信頼を損ない、真の公衆衛生と科学的リテラシーの向上に逆行するものである。
-
 2025/07/14 小島正美
2025/07/14 小島正美HPVワクチンと言えば、「女性の子宮頸がんを防ぐ」とのイメージが強いが、実は海外では男性の接種が当たり前になりつつある。同ワクチンをめぐっては、今、日本で大きな格差が二つ生まれている。男性の接種率の遅れと女性の接種率の都道府県格差の二つだ。
-
 2025/07/14 原田 泰
2025/07/14 原田 泰参院選の争点で急浮上している外国人労働者問題についての各党の政策について考えてみたい。外国人労働者や移民に優しい政党はどこなのか。各党は「多文化共生社会」をどのように考えているのか。
-

『歩く マジで人生が変わる習慣』(池田光史著 ニューズピックスパブリッシング)
2025/07/13 池田 瞬歩くことを包括的にとらえ、 肉体的に動く機能はもちろんのこと、思考や発想との結びつき、都市との関わり、理想的なシューズのあり方とそれをとりまくビジネスの状況などについて深く考察した本である。
-
 2025/07/13 中村繁夫
2025/07/13 中村繁夫私は京都で生まれ育ち、18歳で東京に出て、65歳で再び故郷に戻ってきた。長い年月を経て戻ってきたこの街は、私の記憶にある雅やかで風格ある古都の面影をほとんど残していなかった。代わりに目の前にあったのは、キャパシティー以上の観光客に溢れ、文…
-
 2025/07/12 田中充
2025/07/12 田中充オンラインカジノによる違法賭博が日本のスポーツ界でも他人事ではなくなっている。スポーツベッティングでは、選手や審判に八百長などの不正の持ちかけや脅迫、誹謗中傷などを受けるリスクも伴い、すでに競技によっては処分者や逮捕者も出ている。
-
 2025/07/11 冷泉彰彦
2025/07/11 冷泉彰彦警察庁は、既に改正されていた道交法の運用として、自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する際の反則金額を公表した。今回の決定については、様々な点から見て問題がある。
-
 2025/07/10 大城慶吾
2025/07/10 大城慶吾ステレオタイプな見方で沖縄の現実が一面的に語られていないか。人々の生き方や考え方、多様な歴史にも、もっと目を向ける必要がある。
-

生活保護最高裁判決の舞台裏(後編)
2025/07/10 大山典宏「知る権利」が蔑ろにされるとはどういうことか。そして、「知る権利」を守る最後の砦は何か。生活保護引き下げの最高裁判決は、長く語り継がれるリーディング・ケースとなるだろう。
-

最高裁判決の舞台裏(前編)
2025/07/09 大山典宏生活保護引き下げ裁判は、利用者とそれを支えた原告団の力があったことは間違いない。ただ、それだけでなく、真実を明らかにしようと動いた記者の存在があった。最高裁判決は、ジャーナリズムの勝利としての側面も見逃せない。
-

-

-

|
|
|