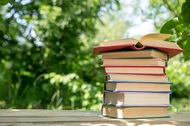-
 2024/08/22 小島正美
2024/08/22 小島正美子宮頸がんなどを予防するHPVワクチンの接種機会を逃した世代の「キャッチアップ接種」が無料で受けられる期限が9月末に迫っている。ただ、いまなお対象世代の半分以上は知らない。このままだと世界から見て、日本が子宮頸がん大国になる。
-
 2024/08/22 大城慶吾,仲上龍馬
2024/08/22 大城慶吾,仲上龍馬原発再稼動は目下、日本のエネルギー政策の最重要課題である。この課題に道筋をつけなければ、日本のエネルギー政策は迷走を続けるままだ。
-
 2024/08/21 山本隆三
2024/08/21 山本隆三トランプ氏は、EVが好きなのだろうか、嫌いなのだろうか。イーロン・マスク氏の支援を受けてはいるが、EVの補助金の廃止を止めるとは発言しておらず、「化石燃料を掘れ、掘れ」とも述べる。市場の動向を踏まえ化石燃料の生産とEV販売の先行きを考えた…
-
 2024/08/21 中西 享
2024/08/21 中西 享東京証券取引所がプライム上場企業に対して、2022年4月から二酸化炭素(CO2)を含む温室効果ガス(GHG)排出量の開示やそのリスク管理やガバナンス体制の見直しなどを義務付けたことなどから、上場企業は環境グリーン対策に追われている。排出量…
-
 2024/08/21 今井悠介
2024/08/21 今井悠介子どもの「体験格差」が広がっている。スポーツ活動、旅行などの「体験」は「贅沢」ではなく、多様な生き方を選択するための「必需品」なのである。
-
 2024/08/20 加藤 学
2024/08/20 加藤 学ロシアが起こした地経学戦争は、欧州の脱炭素政策の欺瞞を露わにした。知らぬ間に日本ばかりが損をしているという状況は避けるべきだ。
-
 2024/08/19 浅川澄一
2024/08/19 浅川澄一介護保険の報酬改定で訪問介護事業者が窮地に陥っている。4月に決まった基本報酬が減額されたためだ。武見敬三厚生労働相は「さまざまな処遇改善加算を新設し、しかも手続きを簡素にしたので支給額は増える」と説明してきたが、現実はそうはではようだ。
-
 2024/08/18 Wedge ONLINE編集部
2024/08/18 Wedge ONLINE編集部フィギュアスケート男子で五輪2大会連続メダリストの元世界王者、宇野昌磨さんがプロスケーターとして新たなシーズンを迎えている。再演のアイスショー「ワンピース・オン・アイス」へのメディア向け公開リハーサルでは、新たな決意を見せた。
-
 2024/08/17 池田 瞬
2024/08/17 池田 瞬夏休みシーズンで、今まさにリフレッシュされている人も多いだろう。いつもの生活パターンやルーティンから離れ、自分の生き方をゆっくり考えるヒントになる3冊を選んだ。
-
 2024/08/17 鉄道クイズ研究会
2024/08/17 鉄道クイズ研究会東京駅の14・15番ホームは、右隣の16~19番のホームより北にずれています。同じ東海道新幹線のホームなのに、そろっていないのはなぜ?
-
 2024/08/16 中岡 茂
2024/08/16 中岡 茂林業のアキレス腱は何かと問われれば、躊躇なく労働安全と答える。単発的だったので社会問題までにはならなかったものの、林業経営を圧迫する要因であり、特に超大林業経営体の国有林では深刻であった。
-
 2024/08/16 WEDGE編集部
2024/08/16 WEDGE編集部高校球児の「聖地」阪神甲子園球場が2024年に開場100周年を迎えた。高校野球では、今年の酷暑対策としての2部制だけでなく、新型コロナ対策や、戦時中に開催された“幻の大会”など、運営方法にさまざまな議論を呼んできた。
-
 2024/08/15 樫山幸夫
2024/08/15 樫山幸夫岸田文雄首相が、裏金問題の責任を取って自民党総裁再選を断念した。後継の予測は困難だが、ひとつだけはっきりしている。新総裁選びの過程、その結果を通じて「新生自民党」の姿を示すことができなければ、国民の信頼回復はおぼつかないということだ。
-
 2024/08/15 秋元諭宏
2024/08/15 秋元諭宏激変する世界情勢の中、米国が日本に期待する役割は大きくなっている。イコールパートナーとしての関係を維持・強化するために必要なこととは。
-
 2024/08/15 鈴木賢太郎
2024/08/15 鈴木賢太郎能登半島地震の被災地では、子どもたちの「声なき声」は届かず、居場所が縮小している。「こどもまんなか社会」を掲げる今、災害対応にも子どもの視点を取り入れる必要がある。
-
 2024/08/14 井原 裕
2024/08/14 井原 裕パリ五輪で日本人選手は多くのメダルを獲得し、躍進した。そのアスリートたちの言葉に注目が集まるが、試合の前は競技に専念したい。試合の後は、休んで、眠って、次の競技に備えたい。試合の前と後のインタビューは負担でしかない。
-
 2024/08/14 中西 享,大城慶吾
2024/08/14 中西 享,大城慶吾オハイオ州立大学の学長に映画『トップガン』のモデルとなった元軍人が就任した。この意義は何か。小誌取材班は大学を訪ね、学長室でインタビューを行った。
-
 2024/08/14 西村則康,辻義夫
2024/08/14 西村則康,辻義夫親子で夜空を見上げるだけでも、雲の流れを追ってみるだけでも、そのときに子どもが感じた「へ~」「きれいだな」「不思議だな」という感覚が、経験として残っていきます。その感覚が、とくに理系の勉強では後につながっていきます。
-
 2024/08/13 田中淳夫
2024/08/13 田中淳夫米国の大統領選挙を報じるニュースで、再びラストベルト(さびついた工業地帯)が話題に上っている。北米西海岸にも、従来の林業や木材産業の衰退で「森のラストベルト」が広がっている。これは日本にもつながる問題である。
-
 2024/08/13 中西 享,大城慶吾
2024/08/13 中西 享,大城慶吾オハイオ州立大学の学長に映画『トップガン』のモデルとなった元軍人が就任した。この意義は何か。小誌取材班は大学を訪ね、学長室でインタビューを行った。
|
|
|